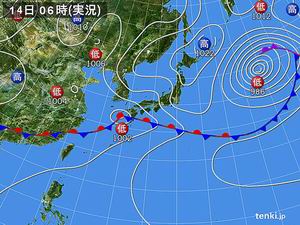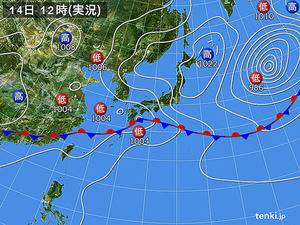| 目国内岳 2022年(令和4年)6月14日 |
山行記録
| 思いもかけない事態に少し慌てたが、 気を取り直して午前6時20分にゲートを出発。 |
||
| 新見峠に向かって歩いて行く。 タケノコ採りで既に何人かが山に入っているようです。 |
||
| 午前7時に峠に到着しました。 |
||
| 当然のことながら駐車場に車はなしです。 |
||
| 少し休んで、入林届に記帳してから午前7時10分に登山口を出発。 登山口は標高737mほどのところです。 |
||
| |
||
| 登山口の脇に一輪のシラネアオイ。 早速見ることができてこの先が楽しみ。 |
||
| |
||
| そこそこの傾斜の道を登って行きます。 タケノコ採りの人もいました。 |
||
| フギレオオバキスミレの群落。 |
||
| フギレオオバキスミレ。 葉っぱがつやつやしています。 |
||
 |
||
| 新緑と青空。 最高の天気です。 |
||
| 登りが緩やかになったところでシラネアオイが登場。 標高900m足らずのところに咲いていました。 |
||
| 昨年、夕張岳で見て以来です。 |
||
| これは少し濃い色です。咲いたところかな。 |
||
| その先にはノウゴウイチゴ。 奥美濃の能郷白山で初めて見つけられたものだそうです。 |
||
| 午前7時40分に三合目を通過。標高900m。 前目国内岳まであと80mほどの登り。 |
||
| 前方に前目国内岳の丸い頂きが見えてきました。 |
||
| 四合目を通過。 |
||
| 山頂が近づいた感じです。 |
||
| 振り返ると南に昆布岳などの山々。 |
||
| 東には白樺山、シャクナゲ岳、チセヌプリなどのニセコの山々。 シャクナゲ岳(右)とチセヌプリ(左)との間に羊蹄山が見えます。 |
||
| |
||
| 前目国内岳山頂直下に咲くシラネアオイ。 |
||
| 午前8時に前目国内岳に到着。標高は980m。 ここで待望の目国内岳の秀麗な姿と対面です。 |
||
 |
||
| 残雪の目国内岳。 (画像をクリックすると拡大されます) |
||
 |
||
| 目国内岳から岩内岳にかけてのたおやかな山並み。 天気も良く期待以上の眺めです。 |
||
| |
||
| 岩内岳の彼方には岩内の町と積丹半島が見えます。 |
||
| 岩内と積丹半島の山々。雪を残した山は余別岳かな。 岩内港の向こうの白い建物は泊原発。 |
||
| 前目国内岳で10分ほど休憩してから先に進みます。 少し下ると道の両側に薄紫の花々が・・・。 |
||
| チシマフウロの群落です。 |
||
| 朝露に濡れたチシマフウロ。 |
||
| 鞍部近くまで下って来るとシラネアオイの群落が続く。 |
||
| 朝日を浴びて元気いっぱいの様子。 しかし今日は風もなく少し暑くなりそうです。 |
||
| シラネアオイの群落(1) |
||
| シラネアオイの群落(2) |
||
| シラネアオイの群落(3) |
||
| シラネアオイの群落(4) |
||
| |
||
| 鞍部を少し行くと沢山の白い花が・・・。 |
||
| ハクサンボウフウの群落です。 |
||
 |
||
| 鞍部から緩く登って行く途中で振り返ると、 前目国内岳とその右後方にニセコの山々が見えました。 |
||
| これまでと違って岩が露出した道になってきました。 |
||
| |
||
| 午前8時55分に岩ノ門を通過。 |
||
| |
||
| 岩ノ門の近くのヒメイチゲの群落。 |
||
| 可憐なヒメイチゲ。 |
||
| さらにその先にはサンカヨウの群落。 |
||
| サンカヨウです。 |
||
| |
||
| 標高が1000mを越えると大きな岩が重なる道になる。 こういうところは歩きにくい。 |
||
| |
||
| 傾斜も少しきつくなってきました。 |
||
| |
||
| 一登りしてから景色を眺めて一息つきます。 羊蹄山が一際高く見えてきました。 |
||
| |
||
| 羊蹄山の右後方に見えるこの山は? |
||
| さらに登って行くとまたまたシラネアオイ。 |
||
| 行儀よく並んでいます。 |
||
| 標高1100m付近。岩の道を登って行きます。 ハイマツも現れてきました。這ってはいませんが・・・。 |
||
| |
||
| だいぶ近づきましたがもうひと汗かかされそう。 |
||
| |
||
| ミツバオウレンの群落。 |
||
| ミツバオウレンです。 |
||
| |
||
| 残雪に出ました。雪の上を行きます。 |
||
| |
||
| しかし、あっという間に登山道に戻ります。 そこには最後のシラネアオイが・・・。 |
||
| 目国内岳最高所のシラネアオイ。 |
||
| 午前9時45分に九合目を通過。 前目国内岳から既に1時間半近くかかっている。思いのほか厳しい登りでした。 |
||
| |
||
| 残雪の彼方に狩場山の雄姿。 |
||
| 山頂の岩場が見えてきました。 あと40mほどの登りだ。頑張ろう。 |
||
| 岩場を登って行きます。 |
||
| 山頂直下は岩が入り組んでいるが、白い目印があり迷うことはない。 しかし大きな岩の登りはしんどいです。 |
||
| イワウメを見ながら一息つく。 |
||
| 午前10時ちょうどに大岩が積み重なる山頂に着きました。 ヤレヤレです。 |
||
 |
||
| 少し休んでから山岳展望。 西の彼方には大量の雪を残した雷電山。 (画像をクリックすると拡大されます) |
||
| |
||
| 雷電山の左遠くは狩場山方面。 |
||
| |
||
| 雷電山の右には岩内岳。その彼方に積丹半島。 調子が良ければ岩内岳までと思っていたが、無理そうなので諦めます。 |
||
| |
||
| 西にはニセコ連峰と羊蹄山。 |
||
| |
||
| 小さな残雪がある前目国内岳から新見峠を経て連なるニセコの山々と羊蹄山。 |
||
| 左手前にチセヌプリ。その右に小さくニトヌプリ。 左にイワオヌプリ。中央に大きくアンヌプリ。そして後方羊蹄山。 |
||
| |
||
| 三角点から先ほどまでいた目国内岳最高点を見る。 目国内岳は標高1220mあるが、三角点は標高1202mの別のピークにあるのでそこにやってきました。 |
||
| |
||
| 三角点は登山道の一通過点のようで居心地は良くないため、 さらに進んで雷電山が見える休憩適地まで来ました。 ここから下ってパンケメクンナイ湿原まで行きたいところだが、 250mの登り返しのことを考えて体調の良いまたの機会にすることにした。 |
||
| 雷電山の右には岩内岳。湿原を経て行くことができる。 次に行くとしたら通行止めのない時を狙って・・・。 |
||
| 午前11時に山頂にお別れをして下山します。 ニセコの山々が雲に隠れてきました。 |
||
| 少しだけですが残雪を下ります。 |
||
| 八合目から山頂を振り返る。 |
||
| 鞍部まで戻ってきました。 あとは前目国内岳への登り返しがあるだけです。 |
||
| |
||
| 鞍部付近のシラネアオイの群落。 見納めです。 |
||
| |
||
| シラネアオイの群落。 |
||
| |
||
| シラネアオイと目国内岳。 |
||
| |
||
| シラネアオイ(1) |
||
| |
||
| シラネアオイ(2) |
||
| |
||
| シラネアオイ(3) |
||
| |
||
| 目国内岳を振り返りながら登って行きます。 |
||
| 午前12時20分に前目国内岳に戻る。 少し休憩していると、目国内岳から下るときにすれ違った札幌から来られた方が登ってきた。 地元の方なのでこの付近の情報をいろいろ教えていただきました。 |
||
| その方が下って行ったあと、 しばらく目国内岳を眺めてから私も下山を続けました。 |
||
| 午後1時10分に登山口に戻る。 登山口のシラネアオイにお別れしてゲートに向かう。 |
||
| 新見峠を通過。 |
||
| 道は工事などをしている様子もなく、 一体何のための通行止めだったのか不明のままです。 |
||
| 午後2時にゲートに戻ってきました。 通行止めというハプニングで一時は慌てましたが、 シラネアオイが咲く秀麗な目国内岳に無事登ることができて良かったと思います。 特にシラネアオイの群落は期待以上のものでした。 好天に恵まれ、所期の目的を達することができて只々感謝あるのみです。 神仙沼・シャクナゲ岳に続く |
| コースタイム |
往 ゲート(6:20)−新見峠登山口(7:10)-前目国内岳(8:00-8:10)−岩ノ門(8:55)−目国内岳(10:00) 復 目国内岳(11:00)−岩ノ門(11:40)−前目国内岳(12:20-12:40)−新見峠登山口(13:10)−ゲート(14:00) |
|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|