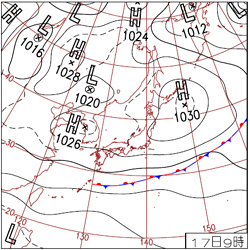| 槍ヶ岳 2008年(平成20年)10月17日 |
山行記録
| 10月17日 | ||
| 上高地BTに午前6時に到着。河童橋まで行き穂高岳を眺める。 |
||
| 西穂高岳に日が差し始める。 |
||
| 河童橋から焼岳を見る。今日はまずまずの空模様のようだ。 河畔のベンチで簡単な朝食をとってから6時25分に出発する。 |
||
| 7時に明神を通過。まだ日が差ささず朝の冷気に包まれた道を徳沢を目指して歩いて行く。 |
||
 |
||
| 梓川の河畔遠くに紅葉した木々が朝日に輝いているのが見えた。 |
||
 |
||
| 7時45分徳沢に到着。今年の紅葉は今一つ鮮やかさに欠けるようだった。 |
||
| 徳沢の近くから昨年登った屏風ノコルを見上げる。 |
||
| 新村橋の前を通過。 |
||
 |
||
| 横尾に向かう途中で前穂高北尾根を仰ぎ見る。 来る度に同じところで写真を撮るが、季節は同じでも天候によってその表情は様々だ |
||
| 横尾に近づいてくると、横尾谷の奥に横尾尾根が見えてくる。 明日はあの尾根を下る予定です。 |
||
| 8時40分に横尾に到着。 ここまで休みなしで来たので小休止をとる。まだ人影は疎らだった。 |
||
| 横尾の吊橋から前穂高を眺める。 |
||
| 横尾谷に通じる吊橋を左に見て槍沢を目指す。右は蝶ヶ岳への道。 |
||
| 横尾からは変化の少ない道が続くため気が緩んで眠気に襲われた。 しかしほどなく槍見河原に着き、そこから槍の穂先を見て気持ちも引き締まる。 |
||
| 槍見河原から10分ほどで一ノ俣を過ぎる。 |
||
| 更に10分ほどで二ノ俣に着く。写真は二ノ俣から沢沿いに少し登ったところ。 |
||
| 沢に沿ってしばらく歩いて行くと道の脇に小さな物置のようなものがあった。 よく見ると水力発電と書いてあった。 |
||
| 緩い坂道を登って槍沢ロッジに向かう。 |
||
| 10時15分、槍沢ロッジに着き小屋の前のベンチで一休みする。 |
||
| 小屋のそばの広場からは槍の穂先が見えた。 |
||
 |
||
| 小屋の対岸の山肌は紅葉の盛りだった。 |
||
| 槍沢ロッジから少し登って行くと右手に槍見と書かれた岩があった。 その岩の上方には槍と見間違えるカブト岩がドーンと聳えていた。 |
||
| その少し先からは、本物の槍ヶ岳を望むことが出来た。 |
||
| 槍沢ロッジから30分でババ平に着く。このあたりから視界が開けて槍沢のU字谷の様子ががよく分かる。 標高は1987m。正面には東鎌尾根が連なる。 |
||
| 槍沢の左岸にそって登って行く。写真は五郎沢付近。 |
||
| ババ平から30分ほどで大曲に着く。標高2094m。 ここから東鎌尾根の水俣乗越までの道が分かれる。 |
||
 |
||
| 大曲から少し登ったところから槍沢を見上げる。正面は大喰岳から中岳に続く稜線。 |
||
| 大曲から1時間ほどで天狗原への分岐点に着く。 標高は2348m。傾斜も徐々にきつくなってくる。 |
||
| 天狗原への道を見る。槍沢の斜面をトラバースして続いている。 明日はこの道を戻って来る予定。 |
||
| 天狗原への分岐付近から槍沢を振り返り遠い昔の氷河に思いを馳せる。 正面の台形の山は赤沢山。その左のピークは西岳 |
||
| 天狗原への分岐を過ぎるとつづら折りの道となる。 分岐から1時間ほどかかってようやくグリーンバンドと呼ばれるハイマツ帯の上に出る。 |
||
| 槍ヶ岳までの道は岩の道だ。肩の小屋が見えているがなかなか近づかない。 |
||
| 槍ヶ岳を開山した播隆上人が53日間修行したという播隆窟。 ここからさらに傾斜の増した岩の道を1時間半近くも登って槍ノ肩に辿り着く |
||
| 肩ノ小屋に宿泊を申し込み、部屋で少し休んでから槍の穂先を登る。 クサリや梯子が設けられているので特に危険なところはない。 |
||
| 頂上に着いたのは午後の4時頃。 36年ぶりのことだったがあいにくのガスで展望は得られなかった。 |
||
| 10月18日 | ||
| 5時半からの朝食を戴いてからご来光をみる。 常念岳の真上からの日の出は6時を少し過ぎた頃だった。 |
||
| 小屋の宿泊客は10数名で、他に自炊客が何人かと海外の登山隊が8人だった。 夜はそれほどの冷え込みもなく快晴の夜明けを迎えた。 |
||
 |
||
| 肩からは裏銀座の山々を始めとして、黒部五郎、薬師、水晶、立山、後立山など 北アルプス中北部の山並みの大展望が得られた。 |
||
 |
||
| 立山遠望(手前は野口五郎岳) |
||
 |
||
| 後立山遠望(白馬、五竜、鹿島槍、爺、針ノ木、蓮華の山々) |
||
| コースタイム |
河童橋(6:25)−徳沢(7:40)−横尾(8:40−8:55)−槍見河原(9:30)−槍沢ロッジ(10:15−10:30) −ババ平(11:00)−大曲り(11:30)−天狗原分岐(12:30-12:40)−槍ノ肩(15:25-15:40) −槍ヶ岳(16:00) |
南岳・天狗原へ続く
|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|