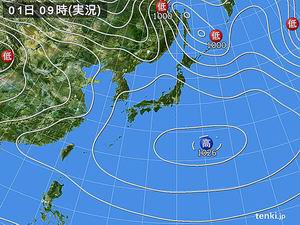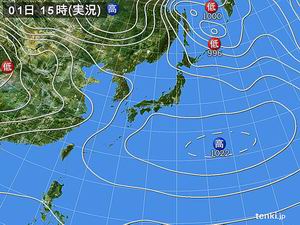| 小雲取越(熊野本宮大社〜小和瀬) 2025年(令和7年)3月1日 |
山行記録
| 熊野の宿から1j間余り走って午前7時過ぎに小和瀬に到着。 支度をして待つこと暫し、小口からのバスが定刻の7時32分に来ました。乗客は私一人でした。 |
||||||||
| バスは赤木川沿いに走って7時42分に神丸に到着。 ここで7時44発の本宮行のバスに乗り換えました。 私を含めた乗客3人を乗せたバスは熊野川沿いの国道168号を快走して行きます。 |
||||||||
| 午前8時10分ごろに本宮大社前に到着。 まだ人がまばらな境内の石段を上って参拝を済ませてから御朱印を戴き、 午前8時35分に小雲取越えを始めました。 |
||||||||
| 石段の様子。 前の二人は外国から来られた方のようで、小和瀬までほぼおなじ行程でした。 |
||||||||
| 本宮大社のあとは大斎原に向かいます。 |
||||||||
| 大斎原への参道を行きます。 |
||||||||
| 大鳥居を潜って大斎原へ。 |
||||||||
| |
||||||||
| 大斎原を参拝したあと国道に向かいます。 |
||||||||
| |
||||||||
| 国道168号に沿って歩いて行くと左手に大峯奥駈道の起点(写真中央付近)が見えてきました。 左後ろには七越峰も。 |
||||||||
| 奥駈道に向かう備崎橋の近くで国道と分かれて山道に入って行きます。 |
||||||||
| しばらく車道を緩く登ってから右に折れて行きます。 |
||||||||
| ようやく熊野古道らしい雰囲気になってきました。 |
||||||||
| 緩く登って10分ほどで湯の峰温泉への道との分岐に着きました。 請川へは左の道を行きます。 |
||||||||
| 分岐からは緩い下りとなる。熊野古道らしい石畳のところもあります。 |
||||||||
| 分岐から10分ほどで再び国道に出ました。 |
||||||||
| さらに10分ほど国道を歩いて請川に到着。午前9時40分。 |
||||||||
| 那智大社から続く番号道標。約500m毎に建てられているらしい。 ゴールの小和瀬は#30の近くなので約12kmかな。また、ここの標高は50mほど。 |
||||||||
| 民家を通り抜け石段を登って行きます。 |
||||||||
| 10分ほどで古道らしくなってきました。 |
||||||||
| #53です。まだまだ先は長い。と言うかこれからです。 |
||||||||
| 30分ほど緩く登って行くと一旦平坦な道となります。標高は200mほど。 |
||||||||
| しばらく行くと何か三角点のようなものがあった。 国土地理院の地図で211.2とされているところ。記号を見るとどうやら水準点のようです。 |
||||||||
| 標高200m程度の起伏の少ない道を進んで行きます。 |
||||||||
| 南奥駈道のように一つひとつピークを越えて行くのではなく、 アップダウンが少ないように巻き道となっているところが多いので歩きやすい道です。 |
||||||||
| 午前10時45分ごろに#48を通過。標高は300mほど。 |
||||||||
| 午前10時50分に少し開けたところに出ました。 案内板には松畑茶屋跡と書かれていた。江戸時代には4、5軒の茶屋があったらしい。 |
||||||||
| |
||||||||
| 名残りの石積が残っています。 |
||||||||
| 松畑茶屋跡で少し休憩したあと先に進んで行くと道は高度を上げて行く。 |
||||||||
| 如法山を巻きながら登って行くと、突然視界が開けたところに出た。 そこが百間ぐらだった。 |
||||||||
| 雲が多かった空も何とか晴れてまずまずの展望です。 左遠くに法師山が見えます。右には果無山脈の山々。 |
||||||||
| 果無山脈。 左に最高峰の冷水山、中央に公門崩ノ頭、右に石地力山などが見えます。 |
||||||||
| まずまずの展望を得てから先に進みます。 百間ぐらから10分ほど行くと左に分岐する薄い踏み跡があった。恐らく如法山への道だろう。 |
||||||||
| その先で林道と交差する。右に行くとトイレがあるようだった。 |
||||||||
| 林道を横断すると小雲取山への緩い登りとなる。 |
||||||||
| 古道は小雲取山の山頂を通らないので、適当なところから山頂を目指す。 薄い踏み跡や赤いテープもあるので間違いなさそう。 |
||||||||
| 午前12時5分に小雲取山に到着。今日初めてのピークです。 |
||||||||
| 山名板。 まわりは木々に囲まれて展望はなし。静かな森の中で暫し佇む。 |
||||||||
| 古道に戻って下って行きます。 |
||||||||
| 下って行く途中に賽の河原地蔵が祀られていた。 一つ積んでは父のため、二つ積んでは母のため・・・ |
||||||||
| お地蔵さんの先に休憩所があった。 石堂茶屋跡と言うところで、かつて2軒の茶屋があったそうです。 |
||||||||
| 石積があるので近寄ってみた。 この付近では砥石が採れたらしいが、石積の中には平べったく砥石のような感じのものもあった。 |
||||||||
| 茶屋跡付近の熊野古道。右に茶屋跡があります。 |
||||||||
| 石堂茶屋跡を過ぎて緩く下って行きます。 |
||||||||
| |
||||||||
| やがて道は桜峠に向かって登って行きます。 このあと、確か斎藤茂吉の歌碑がある#36を通り過ぎたが、そのあたりが峠とは気がつかなかった。 |
||||||||
| |
||||||||
| どこが峠か分からないうちに急なつづら折りの下りとなり、そのあと巻き道を進んで行くと桜茶屋跡に着いた。 ここにも休憩所があったので最後の休憩としました。 |
||||||||
| 午後1時半に桜茶屋跡を出発。小和瀬まであと1時間ほどだろう。 |
||||||||
| 道は基本的には下りで、途中に何箇所かある歌碑を見ながら進みます。 |
||||||||
| |
||||||||
| 途中で1箇所視界が開けたところがありました。 どこの山が見えているのかよく分かりません。一族山や子ノ泊山方面かも知れない。 |
||||||||
| |
||||||||
| 小和瀬への下りの途中には熊野古道らしく石畳が残ったところが多かった。 しかし、下りは滑りやすく雨などで濡れているときはなかなか大変そうに思われました。 |
||||||||
| だいぶ下って小和瀬までもう少しというところに尾切地蔵が祀られていた。 |
||||||||
| #30を通過。もう少しです。 |
||||||||
| 小和瀬の集落の中を下って行きます。 |
||||||||
| |
||||||||
| 小和瀬のバス停前の駐車場が見えました。 |
||||||||
| 午後2時30分に小和瀬のバス停に戻ってきました。 今回は予定どおり無事、順調に終えることができました。 次回は大雲取越で、今回のようにはいかないと思います。事前計画・準備を充分にしたうえで取り組むことにします。 |
||||||||
|
||||||||
|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|