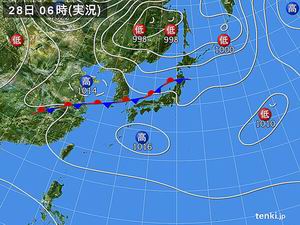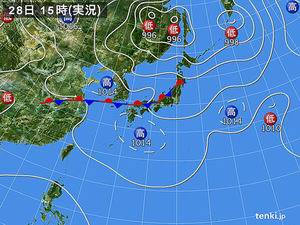| 将棊頭山 2021年(令和3年)8月28日 |
山行記録
| 午前4時45分に駐車地を出発。 まだ薄暗い道を5分ほど歩いて行くと通行止めとなっていた。 |
||
| 小黒川沿いに歩いて道が崩れたところを通過。 まだまだ崩れそうでこのままでは車が通るのは無理なようです。 |
||
| 30分ほど歩いて登山口に到着。 駐車地からここまでの標高差は約200m。思いのほかの登りで早くも汗だくです。 傍らの休憩所で少し休憩し、午前5時30分に出発します。 |
||
| これから胸突ノ頭まで標高差1300mの長い登りが始まる。 |
||
| 20分ほどで”ぶどうの泉”。水量が多く涼しげです。 |
||
| |
||
| このような道を延々と登って行きます。 |
||
| |
||
| 午前6時50分に野田場。ベンチで一休みします。 |
||
| 野田場から坦々と歩いて午前7時25分に”馬返し”。 |
||
 |
||
| 胸突ノ頭から分岐する木曽山脈の主稜線の一つに乗ります。 右に行けば権兵衛峠を経て経ヶ岳まで続く稜線だが、道は生い茂った笹に覆われていた。 |
||
| 馬返しから先は樹相が変わってくる。今の季節では葉が茂って稜線は見えない。 |
||
| 自然林の道を行く。 |
||
 |
||
| はるか遠くに行者岩が見えます。 (標準を拡大しているので不鮮明ですが・・・。) |
||
| このあたりもいい雰囲気です。 |
||
| 午前8時5分に大樽小屋に着く。ここで小休止です。 |
||
| 大樽小屋から15分で胸突八丁。標高は2140mほどのところです。 |
||
| はじめのうちは緩やかな登りが続く。 |
||
| 最後に少し急登して午前9時10分に六合目。 |
||
| 六合目から少し登ると弘法石。 |
||
| さらに登って行くと津島神社。 |
||
| 高度を上げて先行きが明るくなってきました。稜線は近い。 |
||
| 七合目の先にあった石標。三角点でもないようですが。 |
||
| 午前10時25分にようやく胸突ノ頭に到着。 2年前と同じく大樽小屋から2時間かかってしまいました。 |
||
| |
||
| 胸突ノ頭からは稜線直下を歩いて行く。前方に将棊頭山が見えます。 |
||
 |
||
| 午前10時半ごろに主稜線上に出ました。 振り返れば2年前に登った行者岩が見えました。 |
||
| 主稜線を少し登ると分水嶺です。 ここで道は稜線の道(冬道)と稜線を巻く道(夏道)に分かれます。私は眺めの良い稜線を行きます。 |
||
 |
||
| 稜線上には大きな岩が積み重なっている。右手には木曽駒ヶ岳の雄大な姿が。 (画像をクリックすると拡大されます) |
||
| 主稜線の道を登って行きます。 |
||
| 取り敢えず最初の小さなピークに着きました。 ここから見る将棊頭山はなかなか登り甲斐がありそう。 |
||
| |
||
| 次のピークのP2646はその直下を巻いて行きます。 少しお腹も空いてきたので木曽駒ヶ岳を眺めながらエネルギーを補給。 |
||
| 休憩の後はいよいよ最後の登りです。 稜線コースはメインルートではないので道は細々としたものですが、 まわりはハイマツの中に岩が点在する高山的雰囲気に溢れたところです。 |
||
| 山頂が近づいてきました。 |
||
| 振り返れば、登ってきた岩の稜線の先に行者岩と丸い頂きの茶臼山が見えます。 遠くの雲がかかっている山々は北アルプスです。 |
||
| 山頂と思ったピークに立つと、更にその奥に目指す将棊頭山が見えました。 |
||
| 午前11時30分に将棊頭山に到着です。休む間もなく山岳展望を開始。 |
||
| 山頂からは南に木曽駒ヶ岳の雄姿。 右から麦草岳、木曽前岳、木曽駒ヶ岳、中岳、宝剣岳、伊那前岳。左奥には空木岳。 (拡大画像はここから) |
||
| 木曽駒ヶ岳山頂部 (マウスポインターを画像に重ねると拡大されます) |
||
| 乗越浄土と宝剣岳 |
||
 |
||
| 東には南アルプス。眼下に西駒山荘が見えます。 |
||
| 農鳥岳の右には富士山。 |
||
| 東に対峙する甲斐駒ヶ岳。 |
||
 |
||
| 南アルプスの左には八ヶ岳や浅間山。 |
||
| 八ヶ岳核心部。横岳、阿弥陀岳、赤岳、権現岳。 |
||
| 北には北上する主稜線上に経ヶ岳。 |
||
| 茶臼山の彼方には雲に覆われた北アルプス。 |
||
 |
||
| 槍・穂、常念方面 |
||
| |
||
| 常念岳と大天井岳 |
||
| |
||
| 槍・穂高の山頂部は雲の中。西穂高だけは見えています。 |
||
| |
||
| 乗鞍岳 |
||
| |
||
| 西には御嶽山 |
||
| 山頂からの眺めに納得してから標柱のカバーを元に戻して将棊頭山にお別れをします。 |
||
| 帰りは西駒山荘経由で。 |
||
| |
||
| 西駒山荘です。手前の石室は登録有形文化財だそうです。 |
||
| |
||
| 遭難は8月26日から27日にかけてだった。 |
||
| 山荘の前に置かれてあった案内板。貴重な情報です。 |
||
| 山荘の前の広場 |
||
| |
||
| 山荘の前からは北アルプス方面が一望です。 時刻も12時を回ったので名残り惜しいですが下山します。 |
||
| 夏道の途中にはこのような大岩も。 |
||
| 分水嶺に戻ってきました。 寝不足と疲れた状態での車の運転はさすがに危険と思い、 電波が通じる間にホテルを予約して今日は伊那市内で泊ることにした。 |
||
| |
||
| 将棊頭山を振り返りながら胸突ノ頭に向かう。 |
||
| 午前12時55分に胸突ノ頭。これから長い長い下りが始まります。 |
||
 |
||
| 将棊頭山を振り返る。 |
||
 |
||
| 西駒山荘も見えました。 |
||
| 津島神社の御神体? |
||
| ヒカリゴケがあるようですが分からなかった。 |
||
| 弘法石の標柱 |
||
| |
||
| 胸突八丁まで下ってきました。 |
||
| |
||
| 大樽小屋で休憩し、炭水化物を補給してから下りを続けます。 |
||
| |
||
| 馬返しを通過。 |
||
| 野田場で小休止。 |
||
| 午後4時5分に登山口に戻ってきました。 疲れた体には厳しい長い下りだった。 |
||
| |
||
| 車道を歩いて午後4時25分に駐車地に戻る。 12時間近い山歩きで疲れたが、無事戻って来ることができて何よりでした。 今年の夏の山行はこれでお終いです。 |
||
| |
||
| ホテルの部屋からは甲斐駒ヶ岳と仙丈ヶ岳がよく見えた。 |
||
| |
||
| 明くる日も良い天気。 将棊頭山を見納めてから大阪に向かいました。 |
| コースタイム |
往 駐車地(4:45)−登山口(5:15-5:30)-野田場(6:50-7:00)−大樽小屋(8:05-8:15)−胸突八丁(8:30) −六合目(9:10-9:20)−胸突ノ頭(10:25)−分水嶺(10:45)−P2646(11:00-11:10)−将棊頭山(11:30) 復 将棊頭山(11:50)−西駒山荘(12:05-12:10)−分水嶺(12:30-12:50)−胸突ノ頭(12:55) −大樽小屋(14:05-14:25)−野田場(15:10-15:15)−登山口(16:05)−駐車地(16:25) |
|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|