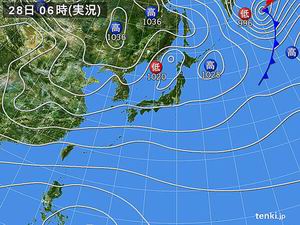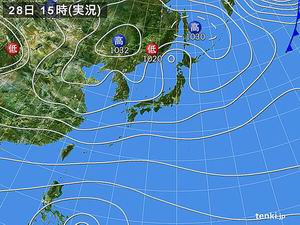| 加茂助谷ノ頭 2022年(令和4年)10月28日 |
山行記録
| まだ暗い午前5時15分にヘッドランプを点灯して駐車場を出発します。 最近熊が出没しているので夜間登山は禁止との看板が立っていた。 今は夜明け前であり、もうすぐ明るくなるのでそのまま登山道に入って行きました。 |
||
| 尾鷲辻まではヘッドランプの灯りや熊鈴の音で自己主張をしながら暗い道を歩いて行く。 およそ30分で無事尾鷲辻の東屋に到着。少し明るくなってきたのでヘッドランプをリュックに収納しました。 |
||
| 尾鷲道を緩く下って行く。 今回は大きく見て前半は下り、後半は登りとなり、通常の山歩きとは逆になります。 |
||
| 西側の谷には雲海ができているようです。 手前の谷は東ノ川あたりだろうか。 |
||
| 午前6時15分ごろ東の空が赤くなってきた。 |
||
| 午前6時20分に尾鷲道と別れて堂倉山に向かう。 |
||
| 堂倉山まで緩い登りとなる。 |
||
| 午前6時30分に堂倉山。ちょうど朝日が差し始めた頃だった。 少し休憩します。 |
||
| |
||
| 休憩したあと地池高に向かうが、下り方向がよく分からない。 あちこち様子を見て回るうちに遠くに地池高と加茂助谷ノ頭と思われる山が見えた。 |
||
| |
||
| GPSで確認してから地池高の方向に向かって下って行きます。 やはり一度来たくらいではダメです。 |
||
| 下って来た鞍部手前付近。倒木が多い。 地図では読み切れない地形で、このあたりも少し分かりにくいところがあった。 地理院地図の一点鎖線から大きく逸脱しないように進みます。 |
||
 |
||
| 前回一点鎖線に忠実に沿いすぎて無理矢理1320mほどのピークに登ってしまい、 大きく時間をロスしたことに凝りて、今回はシャクナゲが密集するそのピークを鞍部から巻いて行きました。 |
||
| 左手には秘境の雰囲気がする眺めがあった。 中央の稜線上に正木嶺の頂上部が少し見えています。 |
||
| 巻き道が終わると地池高との鞍部です。 まわりには伐採され枯れてしまった木の根元が沢山。 |
||
| 鞍部から地池高に登って行きます。 今日初めての本格的な登りですが標高差は50mほど。 |
||
| 登りついてから右に行くとヒメシャラの林がある。 紅葉の時期に見るのは初めてですが、朝日に映えてなかなか綺麗でした。 |
||
| そのあとは狭い岩の尾根を行きます。 前回はこの付近にアケボノツツジが咲いていました。 |
||
| 今日は花はないが紅葉が綺麗です。 |
||
| もう盛りは過ぎているようですがまだまだ見応えはあります。 |
||
| 午前7時50分に地池高に到着。 前回と同じ時間です。 |
||
| 地池高山頂の三角点。 標高は1399mで、堂倉山から始まる支脈上では堂倉山に次いで高い。 因みに、この支脈は加茂助谷ノ頭を経て延々と続き、途中で秀峰仙千代ヶ峰を起こして総門山で尽きます。 |
||
| 山頂からは地倉山とマブシ嶺方面の山がよく見えます。 |
||
| 樹林越しに、光る熊野灘も見えます。 |
||
| |
||
| 休む間もなく先に進みます。急な斜面を下って行くと・・・ |
||
| |
||
| 獣除けネットがありました。この隙間を抜けて行きます。 |
||
| さらに下って行くと前方にP1344の森が見えてきました。 |
||
| P1344との鞍部に下り立ちました。 一帯は伐採跡でまわりの眺めが素晴らしいところです。 これは地倉山方面です。 |
||
| 堂倉山方面。 中央左手前が堂倉山。右奥の高い山は正木ヶ原。(自信はありませんが) |
||
| 振り返るとこれから向かう加茂助谷ノ頭。端正な姿です。 右の丸いピークは無名峰ですがP1300としています。前回の折り返し点です。 |
||
| P1344に向かいます。 枯れた立木の姿が印象的。 |
||
| 振り返ると地池高と鞍部。 こうして見ると紅葉も終盤の感じです。 |
||
| 先ほど見上げた枯れた立木からの加茂助谷ノ頭。 |
||
| P1344からの正木嶺と日出ヶ岳。 右手前は地池高。 |
||
| P1344のピーク付近と思われます。 |
||
 |
||
| ピークの東側も伐採地のようで展望が開けます。 尾鷲から紀北方面の海がよく見えます。 |
||
 |
||
| その左にはP1300から加茂助谷ノ頭と左にテンネンコウシ高。 その間には迷岳方面の山々。 |
||
 |
||
| 迷岳方面です。 右遠くの鋭鋒は局ヶ岳。中央左寄りに迷岳。迷岳の手前には古ヶ丸山も見えています。 左手前にウグイ谷高。ウグイ谷高の左遠くには三峰山。 そして左端に江股ノ頭がちょこっと。 |
||
| P1344から緩く下って行きます。 |
||
| |
||
| P1300との鞍部付近。 |
||
| |
||
| 鞍部付近の紅葉。 |
||
| |
||
| P1300への取り付き付近も伐採地となっていて尾鷲方面がよく見えた。 |
||
| P1300へ登って行きます。 |
||
| (P1300のピークでの写真を取り忘れたので昨年のものを流用します) 午前8時50分にP1300に着く。昨年とほぼ同じ時刻でした。 加茂助谷ノ頭も少し近くなった感じです。 5分ほど休憩してから出発します。ここからは未知の領域です。 |
||
 |
||
| 未知の山は登る時よりも下る時に気をつけないといけない。 この時も地図の一点鎖線に沿うように下って行ったが、 途中から真新しい赤テープが目についたのでそれに導かれるように下って行こうとした。 しかしどうも方向が違う気がしたのでGPSで確かめると、やはり北の広い尾根に入り込むところだった。 |
||
| すぐに軌道修正してヒメシャラの林の中を進み一点鎖線に沿って進んで行った。 油断大敵です。 |
||
| そのあと、一点鎖線が鋭角に折れる小ピークは踏まずに P1276との鞍部(写真)までやって来ました。 |
||
| |
||
| 鞍部とP1276との間にも一点鎖線が鋭角に折れる小ピークが二つあるが、 これもピークを踏まずに二つのピークの間を通り抜けて進んで行きました。 (写真は右側の小ピークの手前から撮ったものです。左方向に進んで行きました。) |
||
| P1300からは明確な尾根筋はなく、 平坦な地形の中をどこでも歩ける代わりに道迷いしやすいところでしたが、 先ほどの二つの小ピークの間を過ぎたあたりからは比較的明確な尾根を行くようになります。 |
||
 |
||
| P1276の手前で樹林が切れて展望が開けました。 尾鷲から紀北にかけての熊野灘がよく見えました。 手前には奥坊主と口坊主も。 |
||
| 午前9時45分にP1276に着きました。 木々に囲まれて特に何もないところです。 |
||
| P1276のまわりはこれまでにない急斜面となっており、下る方向も分かりにくいところだった。 ここなどもGPSがなければ迷いやすいところと思われます。 少し下って鞍部まで来ました。 |
||
| P1276からの下りは木々が密集して少し暗い雰囲気だったが、 鞍部を過ぎると木々も疎らとなり明るくていい感じになって来た。 |
||
| |
||
| やがて右に曲がりながら高度を上げて行くと、 |
||
| |
||
| 開けた空間に出ました。裸の大木が印象的です。 |
||
| そこから少しで前方に青空が見えてきました。 どのような眺めがあるのかと期待感大となります。 |
||
| 午前10時10分。辿り着いた開けた台地からは行く手に加茂助谷ノ頭が端正な姿を見せていました。 おもわず感動の声が出ます。 山頂部は二つのピークからなり、左が与八郎高、右奥が加茂助谷ノ頭です。 また、この広い台地を右に行くと先ほど見た奥坊主や口坊主まで行けるようです。 |
||
| 間近に目的の山を見ることが出来て気分よく進んで行きます。 紅葉は終盤とはいえまだまだ見応えのあるものは沢山あります。 |
||
| 口坊主分岐から歩くこと15分ほどでまたまた眺めの良い開けたところに出ました。 コケ平ともいわれるところのようです。 |
||
| |
||
| 傍らには石碑のようなものがありました。 幾つかの石に取り囲まれた中央の石柱には文字が刻まれていますが判読不可でした。 |
||
| コケ平からは目指す山頂まで近い。 苔むした岩を取り囲むように木が生えています。 |
||
| 紅葉もなかなか綺麗です。 |
||
| 緩く登って行くと、何かカメラのようなものが木に取り付けてあった。 山中に生息する動物を観察・記録しているようです。 |
||
| |
||
| ゴツゴツした岩が増えてきました。 山頂はもうすぐの感じです。 |
||
| やがて目の前に岩山が出現です。 適当なところをよじ登っていきます。 |
||
| よじ登った岩の上には文字が判読不能の古い板のほかには山名表示板のようなものはなかったが、 ここが与八郎高に違いないでしょう。午前10時45分だった。 |
||
| |
||
| 与八郎高の山頂は南北に細長い岩の頂だった。 北の方へ行ってみると、 |
||
| 間近かに今日の最終目的地の加茂助谷ノ頭を見ることが出来た。 時刻も制限時間の午前11時近くになっているので、休憩と展望は後回しにしてまずあの頂きまで行くことにした。 |
||
| |
||
| 岩山を慎重に下って鞍部に下り立ってから山頂を目指して行く。 この付近の紅葉もなかなかのものです。 |
||
| 点在する岩の間を登って行きます。 |
||
| |
||
| 午前10時50分に加茂助谷ノ頭に到着。ほぼ予定どおりの時刻だった。 木々に囲まれてまわりの展望はなかったが、無事辿り着くことが出来ただけで十分だった。 |
||
| |
||
| 山頂には何枚かの山名表示板がありました。 |
||
| |
||
| 岩の上にあった山名表示板。 これは少し古いようで、嘉茂助谷ノ頭と書かれていた。 |
||
| 山頂からの眺めはなかったが、一箇所だけ日出ヶ岳と正木嶺が見える隙間があった。 山頂で10分ほど過ごしてから与八郎高に戻りました。 |
||
 |
||
| 与八郎高で休憩し、お昼ご飯を食べた後は限られた時間でまわりの眺めを楽しんだ。 これは加茂助谷ノ頭の左に見える北の眺めで、右端の局ヶ岳から左端の薊岳までの展望です。 主な山だけでも迷岳、古ヶ丸山、江股ノ頭、大杉国見山、池木屋山、桧塚、明神岳、国見山などが認められます。 未踏の山としては大杉国見山の手前のウグイ谷高をはじめとして多くの山が見えます。 |
||
| |
||
| 迷岳とその手前に古ヶ丸山。 左端遠くには三峰山。 |
||
| |
||
| 手前にウグイ谷高。その左後ろに大杉国見山。右後ろ遠くに江股ノ頭。 |
||
| |
||
| 右の池木屋山から千里峰や千石山、明神岳方面へと続く台高北部主稜線。 その奥には桧塚と奥峰も見えます。 |
||
| 白鬚岳を望遠で。 |
||
 |
||
| 西の彼方には日出ヶ岳と正木嶺。 帰路に林道ルートをとるとあの山を越えて行かなければならない。 なかなか厳しそう。 |
||
| 日出ヶ岳の左には、地倉山の手前に辿ってきた山々が見えます。 |
||
 |
||
| 中央右遠くは地倉山。 手前右端に地池高。左に下って登り返すとP1344。その左手前にP1300。 P1300からは平坦な迷いやすそうな尾根が続いている。左端に口坊主分岐の開けた台地が見えます。 帰路をこのルートとすると越えてきた多くのピークを小刻みに登り返しながら戻ることになる。 どちらにするかはコケ平まで戻ってから決めよう。 |
||
 |
||
| 与八郎高からの眺めの最後は熊野灘。 このあと与八郎高にお別れをして午前11時30分にコケ平に向かって出発しました。 |
||
| 午前11時45分にコケ平に戻ってきました。 |
||
| 帰路をどうするか迷うところですが、 林道に出てしまえばあとはしっかりした道がある林道ルートの方が精神的には楽なので 取り敢えず林道に下る道を調べてみることにしました。 |
||
| 林の中に入って二度ほどルートミスをしましたが、GPSのおかげで何とか目的の尾根に乗ることが出来ました。 尾根にはテープや踏み跡も見られたので、これなら何とかなりそうと思ってドンドン下って行きました。 結局現地の状況を見て林道ルートを選択したことになりました。 |
||
| 下る途中で前方の眺めが開け、テンネンコウシ高へと続くピークと思われる山の裾に 林道がウネウネと続いているのが見えました。 また、ピークの右後ろに日出ヶ岳が、左後ろに正木嶺が見えている。 このあと日出ヶ岳まで登り返すことになるが、気の遠くなるような高さと遠さだった。 |
||
| 尾根を下って行くうちに古い獣除けネットと並行するようになる。 写真のあたりまで来ると下って行く踏み跡のようなものは見られなかったので、 このあたりから左へ降りて行くことにした。 |
||
| 下る途中では明確な踏み跡らしきものはなかったが、 時折テープがあったりしたので大きな間違いはないと思い歩けそうなところを選んで下り続けた。 |
||
| 下り続けること10分ほどで涸れ沢に出ました。 この沢に沿って行けば林道に出るはずです。 |
||
| 涸れ沢に沿って下ること10分ほどで、行く手に林道が見えた時はホッとしました。 |
||
| 午前12時30分に林道に下り立つ。 堂倉山に取り付いてから道なき稜線を辿ってここまで無事来ることが出来た幸運に感謝するのでした。 ここから先もまだまだ長いが、精神的に解放され軽やかな気分で林道を歩いて行きました。 |
||
| 林道を少し歩いて行くと何か建物がありました。堂倉製品事業所だったところのようです。 こちらから見ると少し古い建物ですが、前まで行って見ると全くの廃屋の様でした。 |
||
| 堂倉橋を渡って道はUターンして行きます。 橋からのぞき込むと綺麗な沢でした。この上流で沢は二つに分かれ、 一方は堂倉山に、もう一方は地池高とP1344の鞍部に突き上げて行きます。 |
||
| 橋を渡って少し行くと不気味な構造物がありました。 岩を穿って作られているようですが、誰が何のために・・・? |
||
| 下ってきた尾根の対岸まで来ました。 正面の尾根を下って来たのです。 |
||
 |
||
| 林道から遠くに仙千代ヶ峰が望めました。 |
||
| 林道を歩くこと1時間で大杉谷からの道と交差します。 このあたりの登山道は堂倉坂と呼ぶらしい。 日出ヶ岳まで3.3km。2時間くらいかな。 |
||
| 林道と別れて登山道に入ります。 登山道本線と書かれているが支線でもあるのかな。 |
||
| 堂倉避難小屋。比較的新しいようですが宿泊には使えません。 小屋の横に回ってベンチで休憩してエネルギーを補給してから午後1時40分に日出ヶ岳に向かいます。 山頂まで約500mの登りです。 |
||
| 緩く登って行くこと20分ほどで粟谷小屋からの道と合流しました。 こちらが登山道支線なのかな。 |
||
| しばらくは緩やかな登りが続きます。 |
||
| やがてシャクナゲ坂という急登が始まります。 シャクナゲの中に階段が続く登りで標高差は百数十メートルです。 |
||
| 20分ほど登って行くと最後は岩の登りです。 |
||
| 急登を終えると一旦平坦な道となります。 テンネンコウシ高へ続く尾根が分岐するピークとシャクナゲ平(P1525)との鞍部です。 |
||
| 鞍部から登って行くと遭難碑がありました。 ここで距離的には中間点ですが、標高は1400mほどなのでまだ300mの登りがあります。 すなわちこれまで以上の急登になるということです。いい加減疲れますね。 |
||
| 遭難碑からは鎖もある急登です。 |
||
| しかしそれもすぐに終わってあとは痩せ尾根となります。 |
||
| 痩せ尾根のあとは紅葉が綺麗な穏やかな道。 |
||
| 少し登るとシャクナゲ平(P1525)です。 時刻は午後3時10分。堂倉小屋から登り始めて1時間半です。 日出ヶ岳まであと200m弱の登りが残されているので山頂に着くのは午後4時頃になりそう。 明るいうちに着く見通しはついてきたので疲れないようにゆっくりと行きます。 |
||
| シャクナゲ平から少し下って日出ヶ岳への最後の長い登りに取り掛かる。 |
||
| 一登りしたあと大台ヶ原らしいミヤコザサの笹原に出ました。 遠くにシカが群れており、その中の一頭が物珍しそうにこちらを見ていました。 |
||
| 笹原を通り抜けると標高差150mの最後の登りです。 階段が延々と続きます。ここが我慢のしどころ。 |
||
| 登り続けること25分ほどでようやく山頂が見えてきました。 しかし急がず慌てず、ペースを保って行きます。 |
||
| 午後4時ちょうどに日出ヶ岳に到着しました。 |
||
| 日出ヶ岳山頂です。 |
||
 |
||
| 既に夕刻に近く、山頂は無人で貸し切りでした。 展望台に上って最後の眺めを楽しみます。 これは右の局ヶ岳から左の白鬚岳までの台高の山々です。 |
||
| 右に局ヶ岳、中央付近に古ヶ丸山や迷岳、左に三峰山が見えます。 手前には黒い影となった大杉国見山とウグイ谷高。 |
||
| 白鬚岳方面の眺めです。 |
||
 |
||
| 西には大峰山脈。 山上ヶ岳や大普賢岳、行者還岳などが見えます。左の八経ヶ岳方面は雲の中。 手前の黒い影となった山は三津河落山。 |
||
 |
||
| 弥山・八経ヶ岳方面を経て楊枝ノ森から仏生嶽、孔雀岳、釈迦ヶ岳、 さらには南奥駈の山々が続く。 |
||
 |
||
| 最後に今日歩いた稜線を一望します。 右端にP1344、その左手前に地池高、その左向こうにP1300。 さらに左へなだらかな稜線を辿った果てに加茂助谷ノ頭。 感慨深く眺めました。 |
||
 |
||
| あまりゆっくりもしておれないので午後4時10分に駐車場に向かった。 途中で山頂を振り返ります。 |
||
| 長い階段を下って行きます。 |
||
| まだ紅葉が綺麗な道を戻って行く。 |
||
| 午後4時45分に駐車場に戻ってきました。 今回は長時間の歩行の割には疲労感は少なかった。 これは焦らず、慌てず、急がず、終始一定のペースを保ち続けた結果と思われます。 いづれにしても、念願の加茂助谷ノ頭に登り無事戻って来ることが出来た達成感は大きかった。 駐車場を午後5時過ぎに出発し、往路を戻って帰宅は午後8時前だった。 |
| コースタイム |
往 大台ヶ原駐車場(5:15)−尾鷲辻(5:45)−堂倉山(6:30-6:45)−地池高(7:50)−P1344(8:25)−P1300(8:50-8:55) −P1276(9:45)−口坊主分岐(10:10)−コケ平(10:25)−与八郎高(10:45)−加茂助谷ノ頭(10:50) 復 加茂助谷ノ頭(11:00)−与八郎高(11:05-11:30)−コケ平(11:45)−林道出会(12:30)−堂倉小屋(13:30-13:40) −シャクナゲ平(15:10)−日出ヶ岳(16:00-16:10)−大台ヶ原駐車場(16:45) |
|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|