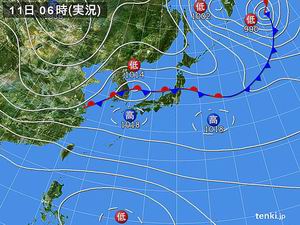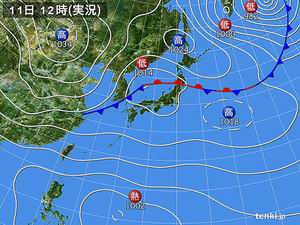| 釈迦ヶ岳・孔雀岳 2017年(平成29年)10月11日 |
山行記録
 |
||
| 午前5時30分に登山口の駐車場に着く。先着の車が1台止まっていた。 そのうち東の空が明るくなり日の出も近くなってきた。 |
||
 |
||
| 朝食をとり支度をして6時ちょうどに出発。 |
||
| 登山口の階段を登って行くと、大峰の稜線が見渡せた。 左遠くには八経ヶ岳方面。右にはこれから辿ってゆく支脈上に古田ノ森と思われるピークが見える。 |
||
| 釈迦ヶ岳から派生する支脈上のP1434に向かって緩く登って行く。 途中で、大きな岩を抱きかかえるようにして生えている大木を見る。たくましい生命力。 |
||
| 比較的緩い登りの道にも途中2か所の梯子があった。 |
||
| 登山口から登ること20分ほどでP1434が見えてきました。 木々の紅葉が朝日を受けて輝いています。 |
||
 |
||
| ほんのりと色着いた紅葉。 |
||
| P1434からのご来光。大峰主稜線上の天狗山方面だろうか? |
||
| P1434から少し行くと特徴ある大日岳の尖峰が見えてきた。 |
||
| 早朝の清々しい雰囲気が溢れる道を進んで行きます。 |
||
 |
||
| 朝日に映える紅葉が綺麗。 |
||
| |
||
| 深い谷筋には雲海ができている。 |
||
| 緩く登って行くと前方に釈迦ヶ岳が見えてきた。 |
||
| 午前6時45分に不動木屋林道からの道と合流する。地図上のP1465。 |
||
| P1465を越えて緩やかに登って行きます。 |
||
| 古田ノ森へ登る途中で木々が途切れた小さなピークに出たので振り返ってみると、 大峰山脈南部の山々が波打つように連なっていた。中央遠くの山は笠捨山と思われます。 |
||
 |
||
| 西の彼方には護摩壇山や伯母子岳などの奥高野の山々。 中央左寄りのなだらかなピークの山が護摩壇山。 伯母子岳は中央右寄りに見えますが、山が重なっており写真では少しわかりにくいかも。右端は夏虫山? |
||
| 古田ノ森(写真ではピークは見えていない)に向かって登って行きます。右に釈迦ヶ岳が見える。 |
||
 |
||
| 登る途中で振り返り見た南の方の眺め。右端の方に小さく登山口が見えます。 |
||
| 古田ノ森に向かって登り続けます。 |
||
| |
||
| 大日岳とその彼方に折り重なる山々。 (画像の上にマウスポインターを置くと拡大されます) |
||
| |
||
| 振り返り見た大峰山脈南部。笠捨山が一際目立ちます。 |
||
| 朝露で濡れたミヤコザサの中を登って行く。釈迦ヶ岳が大きく見えてきた。 |
||
| 古田ノ森までもう一登り。 |
||
| 笹原の彼方に見える大日岳。 |
||
| 午前7時半に古田ノ森に到着。 |
||
| だいぶ近づいてきた釈迦ヶ岳を見ながら古田ノ森を進んで行きます。 |
||
| 途中の小ピークに寄って釈迦ヶ岳を眺めました。重量感のある立派な山容です。 |
||
| 釈迦ヶ岳の左には七面山の向こうに八経ヶ岳。 |
||
| 古田ノ森付近は紅葉が綺麗です。 |
||
| 鞍部を過ぎて釈迦ヶ岳への登りに取り掛かります。 |
||
| |
||
| このあたりもきれいな森だ。 |
||
| |
||
| 千丈平近くの道 |
||
| |
||
| 午前8時に千丈平を通過。この付近はテントサイトとなっている。 |
||
| テントサイト付近にある”かくし水”。乾いた喉を潤しました。 |
||
| 前鬼からの道との合流点。ここまで来れば釈迦ヶ岳までもう少しだ。頑張ろう。 |
||
| 合流点から頂上方面を見る。あと50mほどの登り。 |
||
| 登るうちに樹林が途切れて頭上が明るくなってきた。 |
||
| 傾斜も緩くなり前方にお釈迦様が見えてくると頂上です。 |
||
 |
||
| 午前8時25分に無人の釈迦ヶ岳に到着。いつものことだがCTよりもだいぶ遅れました。 休憩の前に山岳展望を開始。 |
||
| |
||
| 北には孔雀岳から仏生嶽を経て八経ヶ岳へと続く大峰主稜線。 |
||
 |
||
| 孔雀岳と仏生嶽との間には台高山地北部の山々。 5月に歩いた明神岳から池木屋山にかけての稜線や、薊岳、桧塚などが認められます。 左手前には白鬚岳も。 |
||
| |
||
| 孔雀岳の右には大台ヶ原。 |
||
| |
||
| 東には見知らぬ山々が幾重にも。 (画像の上にマウスポインターを置くと拡大されます) |
||
| |
||
| 南には大峰南部の山々。 (画像の上にマウスポインターを置くと拡大されます) |
||
| |
||
| その右手にも紀伊半島の山々が連なる。手前には登ってきた支脈尾根も見えます。 (画像の上にマウスポインターを置くと拡大されます) |
||
| |
||
| 西には護摩壇山や伯母子岳などの奥高野の山々。 十分すぎるほどの眺めを堪能してから腹拵えをして午前8時45分に孔雀岳に向かいます。 |
||
| はじめは急降下の道。帰りの登りが思いやられます。 |
||
| 10分ほどで”馬ノ背”に出る。ここはルート中随一の難所らしいが、張られたロープに沿って行けば大したことはなかった。 もちろん油断は禁物で慎重に進みます。 |
||
| |
||
| 馬ノ背を通過したところでこれから辿る稜線を眺める。 鞍部付近はかなり入り組んでいて、どう辿ってゆくのか全く分からなかった。 |
||
| さらに少し下ったところから孔雀岳と仏生嶽を見る。 |
||
| 鞍部付近には大岩があるため道は稜線から離れて迂回して行く。 |
||
| 迂回路から見た大岩。 |
||
| 迂回路を行く。 |
||
| |
||
| 迂回路の先にも大岩が迫り出している。 |
||
| |
||
| 道はその下部を巻いて行く。 |
||
| |
||
| 10分ほどで迂回路から稜線に戻る。このあたりが釈迦ヶ岳と孔雀岳との鞍部になる。 そこで見えた奇岩はモアイ像。 |
||
| |
||
| 綺麗な紅葉を見ながら稜線を進んで行く。 |
||
| 途中で再び稜線を迂回して行く。 |
||
| 稜線に戻って見晴らしの良い小ピークに出た。そこには”空鉢岳”の表示板があった。 |
||
| |
||
| 空鉢岳からは釈迦ヶ岳の雄姿が目の前に。 |
||
| |
||
| 空鉢岳から七面山を望む。手前は椽ノ鼻から続く岩峰群。 |
||
| 空鉢岳から少し行くと左側が切れ落ちた道になる。 ここは一見何でもなさそうだが、足元は踏み外したら命が危ないところで要注意です。写真はそこから見た奇岩。 |
||
| 午前9時半に椽ノ鼻を通過。蔵王権現が鎮座しています。 |
||
 |
||
| この付近も絶壁となっており慎重に行動する必要がある。 |
||
| |
||
| 椽ノ鼻から見た七面山、八経ヶ岳、仏生嶽。 |
||
| |
||
| 椽ノ鼻から少しで”両部分け”と呼ばれるキレットを通過。ここも要注意箇所です。 |
||
| 両部分けから先はこれまでのような難所はなく、ただ孔雀岳目指して稜線を行くのみです。 しかし道半ばで孔雀岳はまだまだ遠い。 |
||
| 標高は1700mを越えて、孔雀岳までの標高差としてはわずか100mなので頑張っていこう。 |
||
| ミヤコザサの稜線を孔雀岳目指して進んで行きます。 |
||
| あれが頂上だろうか。そうだとするともう少し。 |
||
| この岩を登れば頂上だ。 |
||
| |
||
| と思ったが、登り切って見えたのはまだまだ遠い孔雀岳。一気に疲れがで出てきました。 |
||
 |
||
| 気を取り直して午前10時に孔雀覗きに到着。 |
||
| |
||
| 孔雀覗きから東方面を眺める。足元は深い谷。朝方の雲海は消えていた。 |
||
| |
||
| 南方面。大日岳や笠捨山が見えています。 |
||
| |
||
| 眼下に見える岩峰群は五百羅漢かな? |
||
| |
||
| 孔雀覗きから先はしばらく稜線から離れて苔むした樹林帯の中の道となる。 |
||
| 仏生嶽方面との分岐点。奥駈道は孔雀岳を通っていないようです。 |
||
| 稜線に戻れば今度こそ頂上までは近いはずだ。 |
||
| |
||
| 午前10時10分にようやく孔雀岳にたどり着いた。 この調子では仏生嶽まで行くと登山口に戻るのは夕方近くになるかもしれない。 無理して行けないこともないが、日が短い季節なので万が一のことを考えて今日はここまでとします。 |
||
| |
||
| 孔雀岳山頂から見た大台ヶ原。 |
||
| |
||
| その左遠くには台高北部の山々。釈迦ヶ岳から眺めたものと大きくは変わらない。 |
||
| 大峰北部の山々。稲村ヶ岳や山上ヶ岳、大普賢岳などがよく見えます。 |
||
| |
||
| そして断念した仏生嶽。 |
||
 |
||
| 暫し休憩の後午前10時35分に孔雀岳を発ちます。 |
||
 |
||
| 孔雀覗きを過ぎたところから釈迦ヶ岳を見る。 今朝ほどの透明感はないが、なかなかよい眺めです。 |
||
| |
||
| 孔雀岳(ニセピーク)を振り返る。 |
||
| |
||
| 稜線付近は紅葉真っ盛り。 |
||
| |
||
| 午前11時40分に椽ノ鼻を通過。 |
||
| |
||
| 空鉢岳からの釈迦ヶ岳 |
||
| |
||
| 孔雀岳と仏生嶽を振り返る。椽ノ鼻の岩峰群がはっきりと見えます。 |
||
 |
||
| 馬ノ背を通過。写真で険しさを表現するのはなかなか難しいです。 |
||
| 釈迦ヶ岳への最後の登り。 |
||
| |
||
| 案外短時間の急登で頂上に戻ってくることができました。 |
||
| |
||
| 午前12時35分に釈迦ヶ岳に戻る。無事戻って来ることができてお釈迦様にお礼をします。 |
||
 |
||
| 大峰主稜線の大観を見納めてから釈迦ヶ岳を出発。 |
||
| 綺麗な紅葉を眺めながら下って行きます。 |
||
| |
||
| 午後1時過ぎに千丈平を通過。 |
||
| 古田ノ森に向かって下って行く。 |
||
| |
||
| 釈迦ヶ岳を振り返る。 |
||
 |
||
| 古田ノ森と釈迦ヶ岳 |
||
| 笹原の稜線をドンドン下って行く。右遠くに登山口が見えてきた。 |
||
| |
||
| 不動木屋林道からの道との合流点付近を行く。 |
||
| |
||
| 午後2時10分に不動木屋林道からの道との合流点を通過。このあたりの紅葉も綺麗です。 |
||
| |
||
| 午後2時25分ごろにP1434を通過。登山口に向かって下って行く。 |
||
 |
||
| 登山口近くの道。朝はうす暗くて分からなかったが、この辺りの紅葉はまだ先のようです。 |
||
| |
||
| 登山口手前からの古田ノ森方面を振り返る。 |
||
 |
||
| 午後2時45分に無事登山口に戻ってきました。 予定していた仏生嶽まで行けなかったのは残念だったが、それは次の機会に期待することにします。 いずれにしろ、快晴の好天気の下、綺麗な紅葉を見ながら孔雀岳まで行き、そして無事戻って来ることができたことに感謝です。 |
| コースタイム |
往 旭登山口(6:00)−古田ノ森(7:30)−千丈平(8:00)−釈迦ヶ岳(8:25-8:45)−椽ノ鼻(9:30)−孔雀岳(10:10) 復 孔雀岳(10:35)−椽ノ鼻(11:40)−釈迦ヶ岳(12:35-12:40)−千丈平(13:00)−古田ノ森(13:30)−旭登山口(14:45) |
|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|