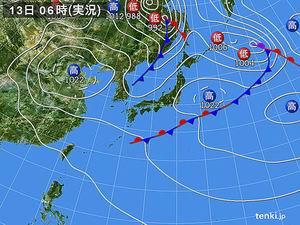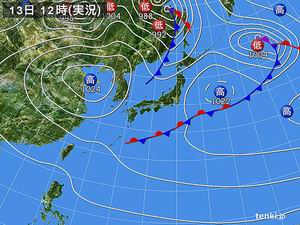| 千石山(奥の迷岳) 2016年(平成28年)5月13日 |
山行記録
| 午前5時40分に登山口の駐車場に着く。車が2台止まっていたが人の気配はない。 今日は平日なので入山者は少ないと思われます。 |
||
| しばらくは車道を行く。がけ崩れ防止のためのモルタルが吹き付けられている。 |
||
| |
||
| 駐車場から15分ほどで登山口のゲートを通過。念のため登山届けを出しておいた。 |
||
| |
||
| 車道の終点付近は崩れ落ちた倒木で塞がれていたので右手に迂回して鉄製の橋を渡って行く。 |
||
| 明神谷に入るとすぐに渡渉が始まる。沢を渡るのは4回で写真は1回目。 |
||
| |
||
| 2回目。特に危険なことはないが結構水量が多く油断は禁物。 |
||
| |
||
| 3回目を渡ったところ。ロープが頼りになるが頼りすぎるのも良くない。 このあと4回目で左岸から右岸に戻る。 |
||
| 駐車場から1時間10分ほどで明神滝。 |
||
| 明神滝を高巻いた後、道は大きなつづら折りの登りとなる。 つづら折りを登りつめる頃にようやく朝日が差してきて新緑が輝きはじめる。 |
||
| このあたりは紅葉のときも見応えのあるところです。 |
||
| 明神平直下の水場を行く。 |
||
| 水場を過ぎれば一登りで明神平です。 |
||
| あしび山荘に7時50分着。私以外無人でした。 |
||
| 抜けるような青空と新緑の大木。 |
||
| 西の彼方には奈良盆地を隔てて金剛山と葛城山。 |
||
| 前山方面へはもう一登り。 |
||
| 山荘前の東屋で一休みしてから明神岳に向かう。 途中で振り返り見た明神平。後ろは未踏の水無山、国見山方面。 |
||
| 今日は前山は割愛して直接明神岳に向かう。途中には瑞々しい新緑の大木が何本も見られます。 |
||
| 道標に書かれているのは桧塚の名前のみ。この付近ではこの山が一番人気があるようです。 |
||
| 三ツ塚分岐を過ぎると大台ケ原方面の眺めが広がる。 その左手前にはこれから向かう笹ヶ峰や千石山も見えます。 |
||
| 手前の平らな山が笹ヶ峰。右に一旦下って登り返すと幾つものピークが並ぶ千石山。 その先は赤倉山以南の山々。笹ヶ峰の背後に池木屋山の山頂部も見える。 |
||
| 明神岳への道。右側は切れ落ちた急斜面。 |
||
| 稜線に咲くミツバツツジ |
||
| 8時30分に明神岳に着く。この付近では一番高い山だが、 展望もなく稜線上の一通過点みたいであまり存在感がない。 |
||
| 明神岳から少し行くと桧塚との分岐に着く。 千石山へは台高の主稜線を辿って行くのだが、殆どの人は支脈上の桧塚に向かうようです。 |
||
| 分岐付近からは大峰山脈がよく見えます。 |
||
| |
||
| いよいよこれまで未踏の台高主稜線に突入する。 前方の樹林の間に見えるのは池木屋山から東に派生する白倉山や迷岳の支脈稜線。 |
||
| 明神岳から15分ほどゆるく下ったあと小ピークに登り返す。 標高1350mほどのところでこのあたりから新緑は一段と輝きを増してくる。 |
||
 |
||
| 稜線上の瑞々しい新緑を仰ぎながら進んでゆく。 |
||
| 小ピークから少し下った鞍部からP1380に登り返す。 |
||
| 登りと言っても傾斜も緩やかで、森の中を散策している気分。 |
||
 |
||
| P1380手前付近。 笹ヶ峰付近は尾根が広く新緑の美しさとあいまって癒しの森という雰囲気。 |
||
| 朽ちた道標。池木屋山と読み取れる文字がある。 |
||
| |
||
| 9時にP1380に到着。ここは笹ヶ峰山頂とされる次のピークよりも10m以上も高い。 |
||
 |
||
| P1380と笹ヶ峰との鞍部付近の森 |
||
 |
||
| 輝く新緑 |
||
| 9時5分に笹ヶ峰山頂に到着。ここで小休止。 |
||
| 笹ヶ峰山頂の道標 |
||
| 10分ほど休憩してから出発。瀬戸越の手前で樹林の間に目指す千石山が見えた。 |
||
| 9時25分に瀬戸越に到着。 吉野川の支流である中奥川に沿ってここまで登って来る道があるようです。 |
||
| |
||
| 瀬戸越を過ぎると尾根はやや細くなる。 |
||
| |
||
| やせ尾根を辿って行くと次の小ピークに着く。 明神岳から千石山までの間には笹ヶ峰を含めて大小五つほどのピークがありここが5番目のところ。 ここを下ればいよいよ千石山に取り付くことになる。 |
||
| |
||
| 鞍部付近から千石山を仰ぐ。標高差は80mほど。 |
||
 |
||
| 千石山へ登る途中で振り返り見た眺め。 右手に先ほど越えてきた明神岳の丸い頂。その手前には笹ヶ峰。 明神岳から左に続く稜線上に薊岳と木ノ実矢塚。さらに稜線の背後遠くに金剛山も。 |
||
| |
||
| 明神岳から右に続く稜線上に桧塚奥峰と桧塚。 |
||
| |
||
| 10時に千石山の三角点に到着。千石山の山頂部には東西に並ぶ三つほどのピークがあり、 国土地理院の地形図ではここ西側の三角点ピークに1380mの標高が記されている。 しかし樹林に囲まれて展望もないので先に進む。 |
||
| |
||
| 細い稜線を辿ってゆく。 |
||
| 2番目のピーク付近の枯れ木。まわりには盛りを過ぎたシャクナゲが咲いていた。 |
||
| |
||
| 2番目のピークからさらに進んで行くとケルンがあった。 ここから右に下って行くと赤倉山から池木屋山へと台高の主稜線を辿ることになる。 |
||
| しかし今日の予定はこの千石山までとしていたので、ケルンの左を直進して3番目のピークに向かいます。 その途中で南西方面の展望が開けた場所に出たので腹ごしらえをかねて日陰で休むことにした。 主稜線はこの先赤倉山、千里峰、奥ノ平峰、霧降山などを経て池木屋山へと続く。 |
||
 |
||
| 大台ヶ原と大峰山脈。近畿の屋根を一望する雄大な眺めです。 |
||
| 大峰山脈の核心部を望遠で。大普賢岳、弥山、八経ヶ岳などが見える。手前には白鬚岳も。 |
||
| 主稜線を下った鞍部には平坦な広場が見える。 |
||
| テントサイト適地かな? |
||
| 大休止してから辿りついた3番目のピーク。10時40分着。 本日の終着点ですが展望はありません。 |
||
| |
||
| しかしこのピークのまわりでは終盤のアケボノツツジを見ることが出来ました。 |
||
| |
||
| 花の数も少ないみたいです。 |
||
| |
||
| 終盤とは言え見ることが出来てよかった。 |
||
| |
||
| 3番目のピークから戻って2番目のピーク付近でシャクナゲを観賞。 |
||
| シャクナゲもピークを過ぎているようで、近くで見ると萎れ始めているものが多かった。 |
||
| |
||
| しかし陽の光を浴びてまだまだ綺麗です。 |
||
| |
||
| 三角点ピークを11時10分に出発して明神岳に向かった。 |
||
| |
||
| 瀬戸越を過ぎたところから江股ノ頭方面を振り返り見る。 |
||
| 11時50分に笹ヶ峰に戻り10分ほど休憩。まわりは静寂そのもの。 |
||
| |
||
| 12時10分にP1380着。 笹ヶ峰やこのピークは東側に広い尾根状の地形を張り出しており、うっかりすると道を間違う恐れがある。 下山時にこのピークで知らず知らずのうちに右の広い尾根に向かってしまい、途中で気がついて引き返しました。 |
||
| |
||
| 明神岳への登り。天気は良いが少々暑いです。 |
||
| |
||
| 12時45分に明神岳を越えて、明神平には午後1時に到着。東屋で一休みする。 相変わらず人の気配がない。今日出会ったのは登りの明神滝と明神平付近でそれぞれ1人。 下りの明神平付近で1人の計3人だった。 |
||
| |
||
| 明神平を午後1時15分に出発して下山を再開。つづら折りの道を下って行く。 |
||
| |
||
| つづら折りの道から沢筋へ。ここは木の橋が架けられて歩きやすくなった。 |
||
| 淡々と下って駐車場には午後2時40分に戻る。 絶好の好天気の下、素晴らしい新緑と花々、そして展望を楽しんだ山行でした。 |
| コースタイム |
往 大又登山口(6:00)−明神滝(7:10)−明神平(7:50-8:00)−明神岳(8:30)−笹ヶ峰(9:05-9:15)−千石山(10:00) 復 千石山(11:10)−笹ヶ峰(11:50-12:00)−明神岳(12:45)−明神平(13:00-13:15)−大又登山口(14:40) |
|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|