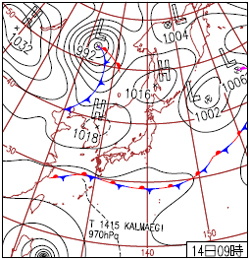| 針ノ木岳・蓮華岳 2014年(平成26年)9月14日 |
山行記録
| 早朝の扇沢駅。 未だ暗いが、私と同じようにヘッドランプをつけて登山口に向かう人もいた。 |
||
| 扇沢駅に向かって左手奥にある登山口。 こんなに暗いうちから歩き始めるのは4年前の三ノ峰以来で4時45分に出発。 |
||
 |
||
| 途中で何回か車道と交差しながら緩く登って行く。 三度目に車道に出たとき振り返ると、遠くに朝焼けに染まる高い山が見えた。四阿山あたりだろうか。 空の雲も予想どおり消え始めている。 |
||
| |
||
| 大沢小屋までの間は、鳴沢岳や赤沢岳の裾を巻いて行く。 樹林の中の道の途中でまだ眠っているような針ノ木岳が見えた。 |
||
| |
||
| 歩くうちに暑くなってきたので、扇沢から30分ほど歩いた鳴沢出会でジャケットを脱ぎ、ヘッドランプもはずした。 さらに巻き道を歩き続けるうちにようやく針ノ木岳に朝日が当たってきた。時刻は5時40分頃。 |
||
| |
||
| 水量豊かな赤沢を上流側のみに手摺りがある木製の橋で渡る。 赤沢岳の稜線に朝日が差している。 |
||
| |
||
| 扇沢から1時間で大沢小屋に着く。小屋はもう店終いしていた。 小屋の裏手に回って朝食をとり、少し休憩する。 |
||
| |
||
| 小屋の右にある大きな岩に張り付けられた道標には、扇沢からここまで3km、ここから針ノ木峠まで4kmと書かれている。 道標の左に小屋を開設した百瀬慎太郎のレリーフもある。 |
||
| |
||
| 大沢小屋からさらに樹林の巻き道を辿ること20分ほどで針ノ木雪渓谷に出る。 まだ日が差し込んでいない暗い谷の奥に朝日に輝く針ノ木岳が遥かに高く聳えていた。 |
||
| 同じところから針ノ木岳をアップ。 まだ雪渓が一部残っているが、もはやその上を歩くことはできないらしい。 |
||
| 樹林の中の巻き道から河原に出たあとは名物の鯉幟の道標が道案内してくれます。 赤沢の橋と同じような木製の橋を渡って右岸に移る。 |
||
| 右岸の道から振り返ると爺ヶ岳から岩小屋沢岳にかけての稜線がくっきりと見えた。 |
||
| 右岸の斜面につけられた道は細かい砂利が混ざって崩れやすい。一歩一歩着実に歩いて行く必要がある。 夏にはこのあたりは雪渓上を歩くことになるのだろう。 |
||
| |
||
| 7時にノドに着く。 残雪が多いときは雪渓を直登していくのだが、今は危険なのでここから左岸に移って高巻いて行く。 |
||
| |
||
| 沢を渡る時に見た雪渓。さすがにこれでは歩けない。 |
||
| |
||
| ノドの高巻き。 鎖が張られた岩を直登する。なかなか険しい。この登りが終わったあともしばらく急登が続く。 |
||
| |
||
| しばらく急登したあとようやく傾斜も緩くなった巻き道を歩いて行く。 途中には秋の花も咲いていた。 |
||
| |
||
| 巻き道を進んで行くとノドノタカマキと書かれた岩があった。 15分ほどかかった高巻きはここで終わり。 |
||
| 右上の写真と同じところから針ノ木雪渓谷を振り返る。 谷からせり上がる稜線上の峰々は、左から鳴沢岳、棒小屋沢岳そして遠くに爺ヶ岳。 |
||
| 7時45分ごろにレンゲ沢を通過。 |
||
| 7時50分に最終水場着。この近くで5分ほど小休止。 ここまで来れば峠まであと1時間ほどか? |
||
 |
||
| 水場から少し登ったところから仰ぎ見た見たスバリ岳。 だいぶ近づいてきた感じがする。 |
||
| 水場からさらに登って行くと谷筋も狭くなる。 ようやく背後の赤沢岳から鳴沢岳、棒小屋沢岳へと続く稜線の高さに近づいてきた。 |
||
| |
||
| 峠までの登りもいよいよ最終段階だ。谷は狭くなり傾斜はますますきつくなってくる。 道は相変わらず岩や砂利混じりで歩きにくい。下りの時が心配。 |
||
 |
||
| 左手の鞍部に峠の道標が見える。 果てしなく続くかのようなつづら折りの登りを終えれば峠だ。あともう少し。 |
||
| 8時35分に針ノ木峠に到着。予定よりも早く登って来ることができたので蓮華岳も視野に入ってきた。 しかし雲が湧き立ってきたのが少し気になる。 |
||
 |
||
| とりあえず小屋の前で休憩する。 ここは峠を絵に描いたようなところで、峠を越える道と後立山の稜線とが交差する。行き交う人は大概ここで足を休める。 |
||
 |
||
| 小屋の前のベンチからは北アルプス中南部の展望が開ける。 こちらも雲が湧いてきているが、まだ眺めは何とか得られそう。 |
||
| 一番に目が行くのはやはり槍・穂高連峰。特に鋭く天を突く槍ヶ岳の姿は均整が取れていて素晴らしい。 9月中旬ともなれば雪化粧を落とした素顔を見ることができる。 |
||
| |
||
| 槍・穂高の右手前は裏銀座の山々だが、雲に遮られてしまったのが残念だった。 手前の山は船窪岳。蓮華岳から烏帽子岳までの稜線のほぼ中央に位置する。 この山域は北アルプスの中でも最も静寂を保つところのようだ。 |
||
| 裏銀座の山々の右手遠くには北アルプス最奥部の水晶岳と赤牛岳。 |
||
| 黒岳とも呼ばれる水晶岳。 この山にも針ノ木岳と同じ宿題を残している。来年は41年ぶりの再訪を果たしたい。 |
||
| 峠での休憩と展望もそこそこにして8時50分に針ノ木岳に向かう。 取り付きの急な登りから蓮華岳を振り返る。山頂のように見えるのは2754mピーク。真下に小屋が見える。 |
||
| 急登を終えると眺めの良い快適な稜線歩きとなる。 |
||
| 稜線上に花はほとんど見られなかったが、 1箇所だけ終わりかけのイワギキョウの群落がありました。 |
||
| 開けた稜線を行く気分は快適だが、体は峠への登りの疲れがあるためなかなかしんどい。 針ノ木岳の上に月齢19.5の月がかかっている。 |
||
| 登っているときはしんどかったが、帰って写真を見ていると苦しかったことは忘れてまた行きたくなります。 |
||
 |
||
| 登りり始めてから約35分。スバリ岳と同じくらいの高さまで来た。 しかしその左後ろに見える山は雲を被っている。もしかしたらあれは剣岳では・・・。 |
||
| 頂上も近くなってきた。あと一登りだ。 |
||
| 振り返ると蓮華岳の全容がようやく見えました。今のところ何とかあそこまで行けそうな時間だ。 |
||
| 37年振りの山頂からの眺めを楽しみにして頑張る。 |
||
| 峠から1時間かけて9時50分に針ノ木岳に到着した。 |
||
| 針ノ木岳山頂の三角点。遠くに見える湖は高瀬ダムの湖。 ダム湖の両側の稜線付近は雲に覆われているが、大天井岳から続く表銀座の稜線や前穂だけは何とか見えている。 (マウスポインターを画像に重ねると拡大されます) |
||
 |
||
| 水晶岳や赤牛岳、薬師岳方面はまだ大丈夫。 |
||
| 水晶岳と赤牛岳。 水晶岳の左には鷲羽岳が見える。また赤牛岳の左の稜線上には黒部五郎岳の山頂部が覗いている。 |
||
| ボリューム感満点の薬師岳。 立山室堂から五色ヶ原経由であの稜線を歩いた36年前のことを思い出す。 |
||
| 薬師岳の右には越中沢岳と五色ヶ原。 |
||
| 五色ヶ原の右には立山と剣岳が続くが、 この方面は黒部渓谷から湧き立つ雲に遮られて山頂部を見ることはできなかった。残念至極。 眼下には白く縁取られた黒部湖。 |
||
| 剣岳をアップ。 二本の雪渓は平蔵谷と長治郎谷と思われます。したがって山頂はその間の源治郎尾根の延長上にある。 山頂部が見えないのは残念だが日帰り登山では仕方ないか。 |
||
 |
||
| 眼下の黒部湖をアップ。右端に黒四ダムの一部が見える。 左端の方には吊橋が見える。これは”かんぱ谷橋”と言い、昔仕事で関わったことがある。 |
||
| この山頂から続く稜線上にはスバリ岳が立ちはだかる。 大勢の登山者が登ってきている。 |
||
| 針ノ木雪渓谷を見おろす。5時間ほどでよく登って来られたと思う。 小さな歩みの積み重ねというのは凄いです。 |
||
| |
||
| 山頂で30分ほど過ごしてから峠に戻る。 下るのはやはり楽で、特に見晴らしのよい稜線の下りは快適です。 これから向かう蓮華岳は雲に包まれかけているが、果たして山頂からの展望は? |
||
| |
||
| 峠に戻ったのは11時ちょうどだった。歩いてきた道を振り返る。 |
||
| |
||
| 15分ほど休憩してから蓮華岳に向かう。 |
||
| |
||
| 蓮華岳の取り付きも急登だった。振り返って針ノ木岳と山小屋を見る。 |
||
| |
||
| 岩の巻き道を登って行く。 |
||
| 急登を終えたあとはたおやかな尾根道となる。 山頂は遠くに見える2754mピークを越えた奥です。 |
||
| 針ノ木岳を振り返る。 雲の動きが速く、眺めが頻繁に変化する。 |
||
| あれが頂上か、と間違いそうな2754mピークを目指す。 |
||
| 2754mピークを越えて平坦な稜線を10分ほど歩いてゆくと、 霧が晴れはじめて蓮華岳の頂きが姿を現わした。 |
||
| 蓮華岳への最後の登り。本日の最後の登りでもあります。 |
||
| 頂上直下。紅葉しているのはオンタデ。 |
||
| 頂上と思って辿り着いたところには小さな祠があった。若一王子神社奥宮と書かれてあった。 |
||
| 蓮華岳の頂上は東西に細長く、奥宮から少し東に行ったところに山頂の標識があった。 峠から1時間ほどで12時20分に到着した。 山頂の東側に設置されている三角点の傍でしばらく休憩することにした。 |
||
| 蓮華岳の頂上のまわりには雲が湧き立っており、遠くの眺めは得られなかった。 写真は頂上から東に続く稜線だが、こちらには登山道はない。 |
||
| 蓮華岳で25分ほど休憩してから下山の途に就いた。 時刻は午後の1時前だが、まだ次から次へと登山者がやってくる。小屋が近いためハイキング気分で登れる山だ。 前方は2754mピーク。 |
||
| 2754mピーク付近を行く。 雲が多くて展望は利かないが、このようなゆったりとした稜線を下るときの気分はなかなか良い。 |
||
 |
||
| 2754mピークを過ぎて峠に向かって下ってゆく。 |
||
 |
||
| 2754mピークを下ったところから見た針ノ木岳。 今日の見納めです。 |
||
| |
||
| 午後1時半に針ノ木峠に戻る。小屋の周りにはさらに人が増えており、今日は超満員のようだった。 休憩して腹ごしらえをしてから午後1時45分に扇沢目指して下山開始。 |
||
| |
||
| 峠直下は砂礫の滑りやすいつづ折りの道だ。滑落すると無事では済まないので慎重に下ってゆく。 |
||
| |
||
| 水場を過ぎてノドノタカマキを下る。 夏場だとこのあたりは雪渓上を歩くのだろう。 |
||
 |
||
| 高巻きからノドを見下ろす。本当に喉のようです。 雪渓上の赤い線は登山の道しるべ。 |
||
| |
||
| 垂直の岩を鎖を頼りにして慎重に下って右岸に移り、流れに沿って下ってゆく。 この辺りは崩れやすい道で、登りの時よりも歩きにくく疲れる。 |
||
| |
||
| 針ノ木雪渓谷を振り返る。 右岸から木製の橋で左岸に移り、小休止してから河原を歩いて樹林の中の巻き道に入る。 |
||
| |
||
| 午後3時40分に大沢小屋を通過。 |
||
| |
||
| 大沢小屋から、登りの時よりも時間をかけて午後4時45分に扇沢に到着。 休憩を含めてちょうど12時間の山行だった。 |
||
      |
||
| 登山道で見かけた花。 稜線上ではほとんど見かけなかったが、針ノ木雪渓谷ではまだ沢山の花が咲いていた。 蓮華岳の頂上手前のピーク付近でコマクサが咲いていたのには感動しました。 |
| コースタイム |
往 扇沢(4:45)−大沢小屋(5:45〜5:55)−ノド(7:00)−最終水場(7:50-8:00)−針ノ木峠(8:35) 針ノ木峠(8:50)−針ノ木岳(9:50-10:20)−針ノ木峠(11:00-11:15)−蓮華岳(12:20-12:45)−針ノ木岳(13:30) 復 針ノ木峠(13:45)−最終水場(14:10)−ノド(14:45)−大沢小屋(15:40)−扇沢(16:45) |
|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|