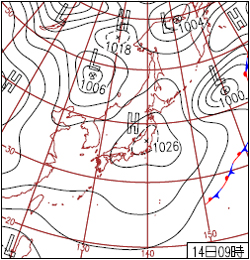| 西穂独標 2013年(平成25年)11月14日 |
山行記録
| 平湯の”あかんだな駐車場”。車も少なく寂しい雰囲気。 6時20分の始発で上高地に向かう。乗客は私を含めて3人のみ。 |
||
| 平湯で5、6人乗せてバスは発車した。 安房トンネルに入る直前に遠くに朝日を受ける笠ヶ岳が見えたので慌てて写真を撮ったが、 ブレた上にピンぼけになってしまった。 |
||
| |
||
| 大正池付近からの穂高岳。左端に独標の稜線が見える。 走行中のバスからなのでピンぼけです。 |
||
 |
||
| 上高地BTには6時50分着。 河童橋から見た快晴の青空の下の新雪に覆われた純白の穂高岳。本当に清々しい眺めだった。 |
||
| 反対側にはこれも上高地からの代表的な眺めの一つである焼岳。 |
||
 |
||
| 河童橋を渡って少し上流側に行ったところから穂高岳を見る。 西穂高から奥穂高にかけての稜線。 |
||
| 河童橋の背後には急峻な六百山が聳えている。 |
||
| 河童橋をあとにして梓川の右岸沿いに西穂高岳の登山口に向かう。 人の気配もなく初冬の雰囲気の道。 |
||
| |
||
| 途中にあるウエストン碑。 |
||
| 振り返り仰ぎ見るとこれから行く独標付近の稜線が見えた。 計画通りに行けば何時間かあとにはあの付近を歩いていることが信じられない高さだった。 |
||
| 対岸の六百山(左)と霞沢岳(右)を眺める。 |
||
| 田代橋から穂高岳を見る。 ここまで来ると前穂高や明神岳もよく見えてくる。 |
||
| 河童橋から30分弱で7時30分に登山口に着く。いよいよ山の中に入って行く。 道はどのような状態だろうか。雪の量はどれほどだろうか。気になるがとにかく前進あるのみ。 |
||
| はじめのうちはうっすらと雪の積もった道を行く。道は明瞭で登りと下りの足跡が一つづつ認められた。 |
||
| 少し高度を上げ、日が差してくるとともに道は階段を交えたつづら折りの急登になる。 |
||
| |
||
| 40年近く前に来た時はこのような尾根道ではなく、沢沿いの道だったような気がしたが記憶違いだろうか。 |
||
 |
||
| 針葉樹林の中の登りは続く。 |
||
| 登山口から1時間あまり登り続けてようやく前方に空が見えてくる。 急登もとりあえず一段落か。 |
||
 |
||
| 急登が一段落すると次は痩せ尾根を行くようになる。このあたりが中尾根だろうか。 この登山道はずっと樹林の中で遠くの眺めはほとんどなかったが、唯一痩せ尾根付近で穂高を見ることができた。 写真はジャンダルムから奥穂高、吊り尾根にかけての稜線。奥穂高岳のピークも見える。 |
||
| 痩せ尾根の途中には写真の桟道などすこし危険なところがある。 9時に通過。踏み外せば一巻の終わり。 |
||
| これは前穂高から明神岳にかけての稜線。 |
||
| 痩せ尾根のあとは再び急な登りとなる。まわりの木々の枝には昨日来の雪が積もったまま。 雪の量も少し増えてきたが歩行には支障がなかった。 |
||
| それよりもゴロゴロした岩の道のようで、雪に覆われているため足を踏み外すことが多く少し歩きにくかった。 |
||
 |
||
| 稜線が近づいてきたのか、綺麗な樹氷も見られるようになってきたが、 このあとも緩急織り交ぜた登りが続いてなかなか小屋が見えてこない。 |
||
| 10時25分にようやく焼岳方面の道と合流した。 しかしここから小屋までさらに15分近く掛かった。この終盤の登りは疲れた体に少し応えました。 |
||
| 樹林を抜けて見通しが利くところまで来た。 乗鞍岳や焼岳の素晴らしい展望が開けてしばし登りの疲れを忘れる。 |
||
| 10時40分にようやく小屋に辿り着いてホッと一息つく。 この登山道は多分マイナーな道なので途中で人に会うこともなかったが、雪の量は大したことはなく、 僅かではあるが踏み跡もあり、道標も随所にあったので不安感なく登ってくることができた。 |
||
| 小屋のまわりには7、8人の登山者がいたのみで、平日でもあるためか意外と少なかった。 小屋の前で腹拵えをし、不要な荷物を物置の棚においてから11時に独標に向けて出発した。 |
||
| 小屋から一登りすると一気に展望が開けた。 正面にはこれから向かう独標や西穂の峰々が険しくも美しい姿を並べていた。 |
||
| 振り返れば焼岳や乗鞍岳。 |
||
| 左手にはこの夏に登った笠ヶ岳から抜戸岳にかけての稜線が続いていた。 その右には双六岳方面の山々が連なる。 |
||
| |
||
| 西穂高の峰々。 一番奥の一際白い西穂高岳(第一峰)から手前に第2峰、3峰と右端の第12峰まで続く。 独標は第11峰となる。 |
||
| 右前方に前穂高から明神岳にかけての峰々が見えてきた。 |
||
| 11時20分に丸山に着く。 今日は稜線上でも風は僅かで日差しもあり、それほど寒さは感じなかった。 しかしこれから先はどうなるかわからない。気を引き締めて行こう。 |
||
 |
||
| 独標への登りから振り返り見た霞沢岳や乗鞍岳、焼岳。 霞沢岳の麓には大正池が見えるが随分小さくなった感じがする。 |
||
| |
||
| 近づいてきた独標。 左に一際高く見えるのは第8峰の通称ピラミッドピーク。 |
||
| 上高地を見おろす。背後は六百山と霞沢岳。その後ろ遠くには中央、南アルプスや富士山。 今朝上高地から朝仰ぎ見た稜線を今歩いている。 |
||
| 私より先行していた2人は途中で引き返したのでそこから先は本日未踏の道だった。 第12峰の手前まで来たが、さすがにこのあたりまで来ると稜線上の道は雪の吹きだまりで膝まで没するところがある。 また雪の薄いところは、その下は凍てついており、迂闊にその上を歩くとすってんころりん状態になる。なかなか厳しいなあ。 |
||
| 第12峰を巻いて独標の手前まで来たが、12峰そのものが岩に雪が張り付いて 氷化しているものもあったりして危険な状態だった。 |
||
| なんとか12峰に登って独標の様子を見る。 アイゼンは持ってきたが、それが利くような状態でもなさそうで、他に対処すべき技術や道具もない。 何かの拍子で滑落すればそれこそ一巻のお終いだ。ということで残念ながらここで引き返すことにした。 |
||
| 第12峰からはこれまで見えなかった奥穂高までを眺めることができた。 |
||
| 奥穂高岳を少し拡大。左に祠のあるピークが小さく見える。 |
||
| 前穂高と岳沢。去年の秋に登った道が微かに見える。 |
||
| 後ろ髪を引かれながら自分の付けた踏み跡を辿って第12峰を下って行く。 途中で2パーティの3人とすれ違ったが、無事登頂できたのだろうか。 |
||
| 下りの途中で見た八ヶ岳。 |
||
| 南アルプスと富士山 |
||
 |
||
| 加賀の白山 |
||
| 西穂山荘には午後1時15分に戻る。ここで少し休憩してから1時30分に帰途についた。 |
||
| 西穂高口に向かって下って行く。 |
||
 |
||
| 途中で西穂高を振り返る。 右端の平らな12峰の左の小さなピークが独標。 |
||
 |
||
| 西穂山荘を振り返る。 |
||
| 西穂高口駅近くにある播隆上人像。 よく見ると左の方を指さしているのでもしやと思って見てみると・・・ |
||
| |
||
| 思った通り槍ヶ岳が見えました。右端の白い山は多分南岳。 |
||
| 2時45分発のロープウェイで新穂高に下る途中で西穂高を見る。 西穂高岳は穂高連峰の中で最も標高が低いが、その険しい姿は連峰の他の峰に決して負けていない。 |
||
| ロープウェイからは槍ヶ岳も見えた。右に大喰岳、中岳、南岳が続く。 |
||
| |
||
| 新穂高からバスで平湯に戻ったのは午後4時30分頃だった。 バスターミナルから”あかんだな駐車場”まで戻る途中で夕日に輝く笠ヶ岳を見る。 期せずして行きと帰りに日の出と日の入り時の笠ヶ岳を見ることができたのは幸運だった。 |
||
| |
||
| 駐車場に戻ってきたのは4時50分頃でちょうど最終の上高地行きのバスが出るところだった。 夕暮れの平湯を5時に出発して往路を戻り、家に着いたのは10時前。 独標の頂きに立てなかったのは残念だったが、念願の初冬の上高地に行くことができ、 また北アルプスの素晴らしい眺めを見ることができたことで十分納得できた山行だった。 |
| コースタイム |
河童橋(7:05)-西穂高岳登山口(7:30)-中尾根(8:50-9:00)-西穂山荘(10:40-11:00)-第12峰(12:20) 第12峰(12:30)-西穂山荘(13:15-13:30)-西穂高口(14:35) |
|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|