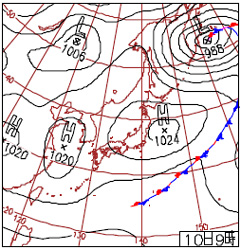| 両神山 2003年(平成15年)5月10日 |
山行記録
 |
||
| 午前4時45分に日向大谷を出発。 登山道は、道路わきに立てられた案内図の横の階段から始まる。 |
||
 |
||
| 階段を登り、民家の庭先に付けられた急斜面を横切る道を進むと樹林の中に入る。 しばらく平坦な道を行き、少し下ると小さな沢に出る。 そこで顔を洗ってまだ残っていた眠気をとり、さらに新緑の平坦な道を進んで行く。 |
||
 |
||
| 信仰の山らしく、道端には随所に石仏や石碑が置かれてある。石碑には波羅波羅童子など何々童子と彫られてある。 七滝沢コースの道を右に分けると程なく大きな沢に出る。このあたりが会所というところだろう。 何回か沢を渡り返しながら緩やかな登りを続けて八海山を過ぎると沢を離れてつづら折りの急登となる。 しかしそれもしばらくの間で、ほどなく道端にニリンソウが咲き乱れる緩やかな登り道となる。 |
||
 |
||
| ニリンソウの群落 |
||
 |
||
| そのうち道は再び沢に沿った登りとなり、午前6時25分に弘法の井戸に着く。 |
||
 |
||
| さらに進んで行くうちに沢には水もなくなり、その行き着く先に清滝小屋の赤い屋根が見えてきた。 二階建ての清滝小屋には6時35分に着く。 何人かの泊まり客が出発の用意をしている以外は人の気配はなかった。 |
||
 |
||
| 産体尾根への急登は小屋の裏から始まる。鈴が坂と書かれてある。 可憐なニリンソウを眺めながらつづら折りの道を登り、途中で七滝沢からの道を併せて、 6時50分に産体尾根の稜線に辿り着く。ここでようやく両神山を眺めることができた。 |
||
 |
||
| 産体尾根を行く。 産体尾根の道は信仰の山らしくクサリやロープを使った登りが何ヶ所かある。 |
||
 |
||
| 樹林の中のつづら折れの道を急登して7時25分に両神神社奥宮に着いた。 |
||
 |
||
| 鳥居の前には一対の狛犬が置かれてあるが、ここのは牙をむいたオオカミの姿をしていた。 |
||
 |
||
| 今は閉鎖されている白井差からの道を併せて平坦な尾根道を行くと東屋跡に出る。 樹林が切れて目の前に山頂が望めた。 |
||
 |
||
| 東屋跡付近からまわりにヤシオツツジが見られるようになる。 盛りは過ぎたようだがまだまだ見応えはある。 |
||
 |
||
| 東屋跡からは尾根道の急登になる。ところどころ道が二つつけられていて、片方にはロープが張られていたりする。 道が二つあるのは、閉鎖された白井差の道に対して別に新しい道を切り開いたためだ。 登山道としてはその閉鎖されている道の方が格段に歩きやすいのでそれに沿って尾根道を登って行く。 |
||
 |
||
| 尾根道を登って行き、最後にクサリで一登りして7時50分に両神山の山頂に着いた。 |
||
 |
||
| 山頂はせいぜい10人位が留まれる程度で非常に狭い。 今日は土曜日だがまだ時間が早く、私以外に単独行の男性が2人いるだけでゆったりとすることができた。 |
||
 |
||
| 天気は良いが、南の方に甲武信岳らしき山がぼんやりと見えるのと、 東の産体尾根が見下ろせる位で、遠くの景色は霞んでいてよく見えなかった。 |
||
 |
||
| 両神山の山頂は稜線上の突起みたいなもので、その両側の東西面は絶壁が続いている。 その絶壁にへばりつくようにしてヤシオツツジが生えており、淡いピンク色の花を咲かせていた。 |
||
 |
||
| 写真を撮るのも一苦労で、下手をすると絶壁を真っ逆様だ。 遠くの眺めは得られないものの、春の陽気に包まれた静かな山頂で至福の一時を過ごして、 8時50分に下山の途についた。 |
||
 |
||
| 産体尾根の取り付きで山頂に最後のお別れをして清滝小屋には9時45分着。 ニリンソウを眺めながら新緑の道を下り登山口には11時15分に戻った。 帰途、薬師の湯に寄って汗と埃を洗い流しさっぱりとした気分になって無事両神山山行を終えました。 |
|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|