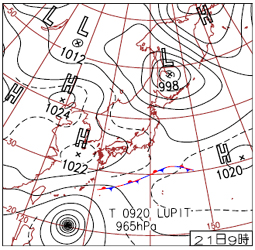| 川上岳 2009年(平成21年)10月12日 |
山行記録
| 登山口には割合広い駐車スペースがあり10台以上は充分駐車可能だ。 天気は良さそうで寒さも思ったほどではない。支度をして6時に出発する。 |
||
| しばらく車道の延長のような道を進んでゆくと大足谷から流れてきた沢に出る。 飛び石伝いに渡って対岸の登山道に取り付く。 |
||
| 沢を渡るとすぐにつづら折りの登りが始まる。 それほどの急勾配ではないので休むことなく歩き続けることができる。 |
||
 |
||
| 高度を上げるほどに樹林の間に乗鞍岳や槍・穂高が見えてくる。 1時間ほど単調な登りを続けてようやく尾根の稜線に辿り着く。 |
||
| そこからは御嶽山の雄大な姿を望むことができた。 |
||
| 一休みのあと尾根上の道を行く。まわりの木々はようやく紅葉が始まったところのようだった。 |
||
| 木々の葉を透かしてみる朝日が眩い。 |
||
| 紅葉の色合いは今一つの感じだが、 木々に囲まれた起伏の少ない尾根上の道は歩いていて気分がよい。 |
||
 |
||
| そのうち道は尾根を外れて山腹をトラバースするようになる。 右手の木々の間から目指す川上岳の稜線が見え出す。 |
||
 |
||
| 起伏の少ないトラバース道を進んでゆくと大木が佇んでいた。 |
||
| 大木を過ぎると道は下りになり、やがて大足谷の源流地に下り立つ。 登山口近くで渡った沢の上流です。 |
||
| |
||
| 一服入れてからいよいよ主稜線に向けて登り始める。一登りで馬瀬村からの道と合流する。 |
||
 |
||
| 背丈ほどの笹の中のつづら折りの道を登ってゆくと乗鞍岳が見えてきた。 |
||
| 登ってきた尾根の稜線の彼方には御嶽山も見える。 |
||
| 笹に囲まれた明るい道をドンドン登って行く。 |
||
| |
||
| P1617では宮村からの道と合流する。川上岳へは右に曲がって少し下って行く。 |
||
| P1617山頂付近の木々。ここの紅葉の色も今一つだが青い空が綺麗なのが救い。 |
||
| |
||
| 下り始めると行く手に川上岳が見えてきた。 稜線付近のドウダンツツジの紅葉が綺麗だが若干くすんだ色合いだった。 |
||
| P1617との鞍部付近からの川上岳 |
||
| 川上岳へ登る途中からP1617を振り返る。ここから見ると鞍部付近の紅葉はなかなか綺麗でした。 |
||
| P1617の右には宮村へ続く道が見える。 |
||
| 鞍部付近の紅葉 |
||
| 川上岳の頂上はもうすぐ。 |
||
| 登山口から2時間15分で川上岳に到着。案外短時間で登ることができた。 |
||
 |
||
| 休む間もなくまわりの景色を眺める。 正面には北アルプス北部の薬師岳から立山、剣岳、大日岳にかけての新雪に覆われた山々が連なる。 |
||
 |
||
| 折から湧きだした雲に姿を隠し始めた穂高岳。 その左には槍ヶ岳と笠ヶ岳が見える。手前の山は位山。 |
||
 |
||
| 振り返ると西の彼方には白山が長大な稜線を横たえている。 北の三方崩山方面から南の大日ヶ岳までが一目で見渡すことが出来た。 |
||
| 白山の主稜線部。右から御前ヶ峰などの主峰群。 ずーっと左には別山。さらにその左には三ノ峰、二ノ峰・・・と続く。 |
||
| ドウダンツツジの紅葉と位山 |
||
 |
||
| 一時、雲に遮られて見えなかった槍穂高も再び姿を現し始めた。 |
||
 |
||
| 頂上で1時間ほども過ごし、まずまずの展望に満足して下山の途に着く。 P1617の登りから振り返り見た川上岳。 |
||
| 大木を過ぎ、トラバース道から見上げた稜線。左にP1617、右に川上岳。 |
||
| 尾根上の紅葉した木々 |
||
| 下山途中で位山を見る。右奥に穂高連峰が見える。 |
||
| 11時35分に無事登山口に帰り着いた。 |
||
 |
||
| 登山口から歩いてきた山々を仰ぎ見る。 川上岳はあの山の向こうで、登山口からは見えていない。 |
| コースタイム (休憩を含む) |
往 登山口(6:00)−御嶽展望所(7:05−7:10)−P1617(8:00)−川上岳(8:15) 復 川上岳(9:30)−P1617(9:45)−御嶽展望所(10:35−10:45)−登山口(11:35) |
|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|