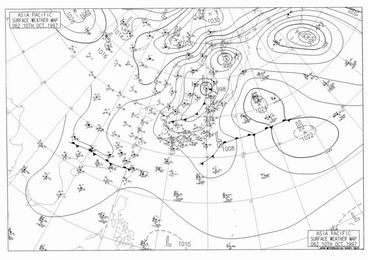| 冠 山 1997年(平成9年)10月10日 |
山行記録
 |
||
| 早朝6時に冠山峠に着く。先着の車が1台止まっていた。 車から出ると風が冷たく少し寒い。冠山の特徴ある山容が逆光の中に黒い影となって見えていた。 |
||
 |
||
| 支度をして6時15分に峠を出発。冠山に向かう。 道は朝露に濡れた笹の間を抜けて行く。ズボンが濡れるので雨具を着て歩く。 |
||
 |
||
| 右手に見える才ノ谷から揖斐川へと続く谷筋は一面霧で埋め尽くされており雲海となっている。 そこから盛んに雲が湧き上がってきて、稜線を越えると消えてゆく。 |
||
 |
||
| 起伏の少ない山道を進んで、短い登りで田代尾根ノ頭を越え、正面に冠山を見ながら稜線を行く。 |
||
 |
||
| 途中、樹林の切れ間から幾度か冠山が望まれたが、進むにつれてその山容は変化して行く。 |
||
 |
||
| 冠平に近付くと紅葉もだいぶ色づいてくる。 |
||
 |
||
| 田代尾根の頭から数回登り下りを繰り返し1時間はどで冠平に着いた。 冠平は、冠山から若丸山へと続く稜線上の笹に覆われた鞍部にあり、 夏には花が咲き乱れるとのことだが今は見る影もない。 |
||
 |
||
| 山頂への道は岩場が多く、ロープが張られてあったりして結構急な道だが、10分ほどで稜線に出た。 そこから左に少し行ったところが三角点のある山頂で7時45分に到着。 笹や喬木を切り開いた狭い、いかにも頂上らしいところだった。 |
||
 |
||
| ここまで来るあいだに空も晴れ渡り、雲の動きも穏やかになってきた。 南側には眼下の雲海を隔てて奥美濃の山々が連なっている。手前の尾根には冠山峠から続く林道が見える。 |
||
 |
||
| 揖斐川源流の雲海と奥美濃の山々。 未踏のものばかりでどれがどれだか見当がつかないが、多分笹ヶ峰から三周ヶ岳、千回沢山あたりだと思います。 |
||
 |
||
| 雲海は揖斐川の流れに沿って延々と続いていた。 |
||
 |
||
| 東の方には若丸山へと続く越美国境稜線。右遠くに能郷白山。 |
||
 |
||
| 能郷白山を拡大。 6月に登った能郷白山はやはり他の奥美濃の山とは桁外れの大きさだった。 |
||
 |
||
| 北東の遥か彼方には加賀の白山が新雪を頂いて雲に浮かんでいる。 |
||
 |
||
| その左手前には部子山と銀杏峰が仲良く並んでいるのが目につく。 |
||
 |
||
| 眼下には冠平(手前)と国境稜線。 |
||
 |
||
| 西の彼方には雲が切れた金草岳。手前に冠山峠と林道。 |
||
 |
||
| 冠平からの冠山。 山頂を1時間ほど一人占めして展望を楽しんだあと8時45分に下山の途につく。下り際に初めて二人連れの登山者とすれ違った。 冠平で冠山の写真を撮ろうと若丸山につづく尾根道を稜線の方へ向かったが、 道は途中から背丈ほどもある笹の中に消えてしまい、なかなか前に進むことが出来ず、あきらめて途中で引き返した。 |
||
 |
||
| 揖斐川へ下る林道から見た冠山。 冠平を9時10分に出発し、往路を戻って冠山峠についたのは10時。 途中で多くの人とすれ違いながら峠に戻ると車と人でいっぱいで、さらに続々と到着していた。 少し休憩してから10時30分に峠を出発する。帰りは岐阜の方へ向かい、対向車に注意しながら坂道を下っていった。 |
|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|