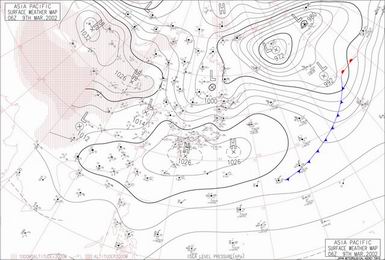| 金糞岳 2002年(平成14年)3月9日 |
山行記録
 |
||
| 中津尾第二登山口を8時25分に出発。 この時期の雪にしてはかなり綺麗で、新雪のようだった。多分数日前に降り積もったものだろう。 |
||
 |
||
| 小さなつづら折りの道をしばらく登ると、尾根に沿った緩い傾斜の雪道となる。 左手には樹々の梢を透かして白倉の頭から続く白い稜線がちらちらと見える。50分ほど歩いて9時15分に林道第二出会いに着く。 ここでは林道は雪に埋もれてしまって全く見えない。これまで金糞岳に登った中で今日が一番雪が多いようだ。 前方の白倉の頭や背後の琵琶湖を眺めながら休憩する。天気が良いため寒さは感じない。 |
||
 |
||
| 林道出会いから一登りで9時30分に連状の頭に着く。ここで漸く金糞岳を見ることが出来た。 右手前には小朝ノ頭も見える。 |
||
 |
||
| 連状の頭から少し下り、小朝ノ頭との鞍部から雪の斜面を登って行くと小朝ノ頭に着く。10時ちょうど。 小朝ノ頭からは正面に金糞岳と白倉の頭の雄大な姿を望むことが出来た。 また東の方には中央アルプス、御嶽、乗鞍、穂高、白山などの中部山岳の山々が眺められた。 白山の手前には能郷白山や蕎麦粒山などの奥美濃の山々が幾重にも重なっている。 少し霞がかかっているようだがまずますの眺めだった。 |
||
 |
||
| 前回の山行の時は強風が吹き荒れ、林道歩きの疲れもあってここで引き返したが、 今日は無風状態で天気も良い。しばらく眺めを楽しんでから金糞岳目指して行くこととした。 少し行くと金糞岳までのルートが一望できるところに出た。なかなか登り応えがありそうだった。 |
||
| まずは鞍部に向かって雪の斜面を駆け下りて行く。鞍部から幾つかの起伏を越えて10時30分に金糞岳の登りに取り付く。 程々に雪が積もった斜面は思ったよりも歩きやすい。樹林の中の急登を終えて緩やかに登って行くと、 今度は少し急な斜面のつづら折りの登りとなる。まわりの樹々も疎らになってきている。 小さなこぶを左に巻いて雪の稜線を登って行き、11時に頂上に着いた。 4年振りに訪れた頂上は一面シュカブラの縞模様で飾られた雪に覆い尽くされ、まばゆいほどの明るさで白く広がっていた。 |
||
 |
||
| 11時を過ぎて陽が高くなり、霞も取れて眺めは申し分ない。 金糞岳の隣にはその名のとおりの白倉の頭。 |
||
 |
||
| 南には伊吹山と右後方に鈴鹿の霊仙山。手前には越えてきた小朝ノ頭。 |
||
| |
||
| 東には遠く御嶽山。 手前は小津権現山(右)と花房山(左)。 |
||
 |
||
| 北には奥美濃の山々が波打つように続く。 左に横山岳、中央右に一際白い上谷山、その右に三国岳。 |
||
 |
||
| 左に上谷山と三国岳。中央右に三周ヶ岳、黒壁山、美濃俣丸や笹ヶ峰が続く。 |
||
 |
||
| 左端に三周ヶ岳。黒壁山、笹ヶ峰、烏帽子山などを経て、金草岳、千回沢山、冠山、若丸山など。 冠山の後ろには部子山と銀杏峯。 |
||
 |
||
| 部子山と銀杏峯の手前の冠山の右に若丸山を経て能郷白山。 その後ろには大きな加賀の白山。 |
||
 |
||
| 白山と能郷白山。 白山の手前には蕎麦粒山と五蛇ヶ池山が見える。 |
||
 |
||
| 奥美濃の山々の次は中部山岳の展望。 まずは北アルプス。右遠くに穂高、槍。左に笠ヶ岳が続く。左端は黒部五郎岳。 |
||
 |
||
| 中央アルプスの木曽駒ヶ岳から南駒ヶ岳まで。 |
||
 |
||
| 最後は南アルプス(左から悪沢、赤石、聖)と恵那山(右端)。 山頂の風はそれはど強くはないがやはり冷たい。写真を撮った後早々にお弁当を食べ、 いつまで見ても見飽きない眺めに別れを告げて12時に下山を始めた。 雪道の下りは早く、林道第二出会いには1時に着く。昼を過ぎて雪も柔らかくなり、時々足を取られて転んだりしながら登山口には1時30分着。 ここから単調な林道歩きが始まる。延々と続く道を戻って2時15分に駐車地に帰り着いた。 |
|ホーム|地域別山行一覧|年別山行一覧|